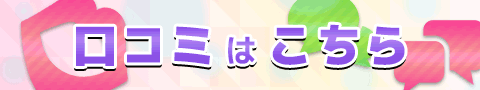6/5 15:30 UP! 愛されてる#2 YUYU(ユユ)(29)
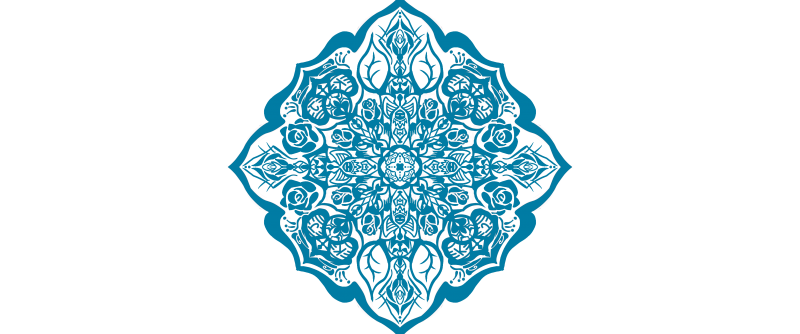
14歳の初夏
部活もあと少しで引退、義務教育の終わりが近づき、今のままの自分ではいられなくなる。名前の分からない不安と焦りに急かされながら、肌を焦がす太陽よりも暑く、興味と情熱が体を熱くして走らずにはいられない。使い道の分からない体力が無限に湧き出して、消せない熱に狂わされ、大きく笑って、大きく悩んで、大きく泣いていた。
土曜日の部活の帰り道、セミの声が空から降って、太陽の光を反射した田んぼが緑に光って眩しい。同級生の若尾ゆりと僕の二人は肩がくっつく距離で自転車を押してゆっくりと歩いてる。目の前の信号機の先はお互い別の道に別れて家に帰る。今は信号機が青だから二人はゆっくり歩いてる。僕とゆりは恋人同士なのか分からない。休みの日に二人だけで出かけた事もない、ただ土曜日の部活の帰り道を二人で歩くそれだけの関係だった。好きだなんて言った事も、言われた事もない。しかし学校に何人も女性がいるが僕のほっぺたに温度を与える女性はゆりだけだった。ゆりと話していると親も友達も自分も知らない僕が心の舵をきる。ゆりが僕の名前を呼ぶだけで言葉が止まって、授業中にゆりが先生に答えを求められると、僕も一緒に汗をかいた。きっと僕達二人は時間と共に関係を深めて、結婚して、子供を作って、同じ時間の中で歳をとるんだ、そんな未来が決まり事のように鮮明に見えていた。
今日僕は決めていた、二人の関係を前に進めようと。次の月曜日二人で一緒に学校に行こう、そうゆりに伝えようと決めていた。二人で登校すれば周りのみんなに僕達の関係が特別だとばれてしまう。ゆりが嫌だと言ったら、僕はどんな顔をすればいいのだろうか?僕の中に流れる特別な気持ちはゆりの中にも流れているのだろうか?ゆりに一緒に登校しようと伝えるのは怖かった、しかし部活の引退が近づき、二人だけで帰れる土曜日はもう数回しか来ない。だから今日伝えようと覚悟を決めたのに、ゆいの話に相槌しか打てずにいる。 信号の色が赤に変わって僕達は立ち止まる。この信号が青になれば二人だけで話せるのは次の土曜日だ。ゆりの会話を止める“あのさ“が僕の渇いた口からずっと出て来ない。きっと信号はすぐに変わる、だから今ゆりの話を遮ってしまおう、そう決心してゆりの話を聞いていた。
「ほんとに最悪なんだよ、私もうお父さんと口きかない、だってさ、私の誕生日のプレゼントはシベリアンハスキーがいいってずっと言ってたの。それで誕生日の日にお父さんがハスキー犬を買って家に連れてきたの。初めて見たハスキーがすっごい可愛かったんだけど、首輪にゴン太って書いてあって、お父さん私の犬に勝手に名前つけてたの、ありえなくない?私ペットにはラッキーって名前つけるって決めてたの、それなのにゴン太って意味わかんない、マジで私お父さんの事嫌いになっちゃって二日口聞いてないんだよね、本当にムカつかない?ねぇ聞いてるの?」
ゆりの話が終わって、部屋の電気を急につけられた気持ちだった。僕の口から考えるよりも早く言葉が出た。
「愛されてるじゃん」
その言葉を聞いてゆりが大きく笑って言った。
「今そーいう話じゃないじゃん、ユユってすぐにボケるから会話になんないよ。」
「それってムカつく話?」
「ムカつくって言ってるんじゃん、ねぇ話聞いてたの?」
きゅうに部屋の灯りをつけられた、僕が話している相手は鏡だったんだ。ずっと見えないフリをしていた、一生懸命に手繰り寄せていた紐の先には何もついていなかった。僕がしているのは恋愛なんかじゃなくて妄想だった。その事に今気がついて僕は叫びたい気持ちを飲み込んで、震える唇で言った。
「俺何があっても親を嫌いなんて言えないよ。」
「急になんの話?」
「なんかゆりと話してると痛いんだよ。」
「なんで泣いてるの?」
ゆりに言われて初めて自分が泣いてる事に気がついた、気がついた時にはもう涙は止められなくて、こんな顔をゆりに見られるのが恥ずかしくて僕は信号が赤なのに交差点を渡ろうとした、そんな僕の服を掴んでゆりが叫ぶ。
「行かないで、」
「やめて」
「どうしちゃったの?急になに?こんな感じでバイバイしたくない」
僕はゆりの聞いたことのない声に驚いて立ち止まった。喉を裂かれたような声を聞いて罪悪感と心配が僕の言葉を奪う。ゆりが下を向いてセーラー服の裾を両手で握りしめて、セーラー服と同じぐらいシワのよった顔で話だす。
「分かんない私、、、ユユ自分の話しないし、いつも私ばっかり話してる、、、分かんないよ、なんで優しいの?なんで私と一緒にいるの?ユユ私のこと好きなの?」
「好きだよ、愛してるんだと思う、、ゆりと結婚したいって考えてた、、、」
「、、、じゃあなんで泣いてるの?」
「ゆりの話を聞いてると、怖いんだよ」
「分かんない、いつもユユが分かんない。」
「俺も分かんないよ。」
「これお母さんがユユのために買ってくれたやつ。ずっと恥ずかしくて渡せなかった、、、これあげる」
ゆりが渡したのは必勝って刺繍がしてある踵のサポーターだった。僕が剣道部の練習で痛めた踵のことをゆりはどこかで知って、心配をしてくれていたんだ。僕はずっと欲しかったサポーターを強引にゆりの自転車のカゴに入れて叫んだ。自分では抑えられない熱と音を出すように。
「いらねーよ、こーゆーのが嫌なんだよ、、、こんなに違うのかよ」
「どうして、、、、」
触れるのも怖いほど大切なゆりの表情が壊れた。僕は自転車に乗った。ゆりは何も言わなかった。出口を塞いだ怒りと、恐怖と、悲しさ、罪が自転車のペダルを踏み下す。考えることを放棄して一心不乱に自転車を漕いだ。すごいスピードで。考える事を放棄したから写真のようにゆりの表情が頭に張り付く。その写真を剥がすように自転車を漕いだ。そごいスピードで。助けが欲しくて何か歌を歌おうとしたが、嵐や大塚愛思い付くのはゆりの好きな曲がかりだった。気がつけば僕は止まってしまいそうな自転車をふらつきながらゆっくりと漕いでいた。
団地の駐輪場に自転車を止めて、団地の階段を登る。1階も2階も3階もどの家も玄関のドアをあけて家の中に風を通していた。僕は4階にある自分の家の前に立って呼吸を整えた。青いペンキが剥げて、所々が錆びた重たい鉄のドアを恐る恐る開けて、音がしないようにゆっくりと閉める。まだ16時なのに暗い玄関でそっと靴を脱ぐ。
「靴履いたまま入りな」
僕は背中で聞いた小さな小さなかすれた声にびくついて急いで振り返った。そこには姉がいた。僕は姉の顔を見て少し安心して促されるまま靴を履いて玄関を上がる。廊下には、割れたガラスのコップと壊れた扇風機の部品が散らばっていた。何がおきたのかは想像できる、でも想像はしないようにした。
僕と姉は二人で寝室に入った。しっきっぱなしの3枚の布団。まだ太陽が沈んでいないのに、僕と姉は隣に並んで布団に入る。夏なのに顔まで布団をかぶって寝たふりをした。あと少し、あと少しすれば布団から出られる、だから僕と姉は二人で寝たふりをしていた。すこしすると寝室のふすまがピシャンっと大きな音を立てて開いた。
「おい、ユユおまん帰ってきたずら?こっち来て一緒に酒でも飲め」
そう言って部屋に父が入って来た。父はひどく酔っぱらっていて真っ赤な顔で目が座っていた。寝癖だらけの茶髪に伸ばしっぱなしの髭、上裸に白なのか灰色なのか分からないジーパン姿。父はもう半年仕事をしていない。
ハウスメーカーが山梨にも入ってきて、父が親方をしている工務店で残っているのは父だけだった。毎日父は朝起きて黙ってテレビの前で積み木をぼーといじってる。その積み木は、病室から出られない妹のために木を触らせたいと祖父が作った積み木で、妹が飽きて手放した物だった。父はその積み木を積んでは崩していた。家から出ずに朝から酒を飲んで、夜を待たずに酔い疲れて寝る。借金を抱えて、彼女と別れて、家に帰ってきてそんな毎日を半年続けていた。父はベロベロになるまで言葉を口にしなかった。ずっと家族に背中を向けて黙って酒を飲み、急に物を壊す。そんな父の背中を僕は見れなかった。なにかの理由を探して酒を飲む。理由がないと寝むる場所もなくて、理由がないとプライドを守れなくて、理由がないと家族とも話せない。酒を飲む父の背中は、なにかにひっしだった。枯れそうな花に酒を飲ませる父を、僕は見れなかった。
「おい、ユユおまん帰ってきたずら?こっち来て一緒に酒でも飲め」
そう言って父が寝室に入ってきた。僕と姉は布団を顔までかぶって寝たふりをしていた。あと2時間もすれば父は酔い疲れて眠ってしまう、それまでの我慢だった。
「おい、聞いてんのか?」
怒鳴る父は寝たふりををする僕の髪の毛をつかんで、草むしりみたいに、すごい力で僕を引っ張り上げた。僕は痛くて甲高い声になりながら父に言う。
「痛い、やめて、部活で疲れてるの、寝かせて。」
「なんだぁ?こっち来りゃぁいいじゃんか?」
「やだ」
「んだぁバカが」
父がそう言って僕の髪の毛を離し、枕元に置いてあった時計を投げて壊した。家族の写真がはめこんである時計を。姉は布団をかぶって声を出さずに泣いていた。これが僕の日常、なにも特別ではない。最近家に帰って来ない姉、居場所の無い父、寝顔しか見ない母、白血病で家にいない妹、これが僕の日常、なにも特別ではない、明日も続く日常。
僕は壊れた時計を拾ってゆりの事を考えてた。ゆり、あなたの愚痴を聞いていると痛いんだよ、自分が幸せじゃないって言われているようで。美しくて優しい君に見せたくなかったんだ自分を。重ならなかったんだ二人が。
次の日の日曜日の朝、母が夜勤のパートから帰ってきて朝ご飯の支度をしていた。父と姉は寝ている。まだ活動を始めていない静かな日曜日の朝、こんな朝早くに起きてくる僕を不思議そうに見ながら母が言った。
「はやいじゃん、部活の試合でもあるの?」
僕はずっと言おうか悩んでいたことを言った。
「俺、高校行かないで働くよ」
「働くって、、、なにかやりたいことでもあるの?」
働きたい訳ではなかった。しかしもうこの道しか無いってうすうす気が付いていた。僕が働けば母に楽をさせてあげられる、それにゆりとあんな別れかたをしてもう学校生活に憧れも未練も無くなった。子供の頃からずっと父が帰って来れば幸せになるって思ってた、でもこの半年間ずっと僕は布団をかぶって隠れてた。父が呑んだくれるのも時間がたてば解決すると思ってた、でも助けになんて誰も来なかった。笑いたいときにはいつも回りに人が集まって、泣きたいときは誰も来ない。先生だって友達だってゆりだって泣きたいときにはいつも来ない。ゆりに告白できなかかったのがこの家のせいなら、父も母も姉も妹も、みんな一人になってるんじゃないのか?僕が働けば家族が少しでも笑うんじゃないのか?誰も助けに来ないのなら僕が家族を助ければいいじゃんか。だから僕は母に言った。
「俺が働かないと、どうにもならないだろ、、、妹が帰ってきたらどうするの?帰りたいかここに?」
「そんなこと考えないでいいの」
「そんなことって、、、」
「大丈夫、お母さん昼も働くから、そんなに心配することじゃない」
「そんなに働いたら死んじゃうよ、、、俺が働けば少しはましになるでしょ」
「いいの、あんたは部活の引退も近いでしょ?今はそれに集中してな。家の事は考えなくていいから」
「考えるよ、考えるだろ、お父さんが壊した炊飯器を買い換えられなくて土鍋でご飯炊いてるんだよ、あんが帰ってきたら来年は中学生だよ、部活やるのにだってお金かかるよ。」
「大丈夫だから、」
「なにが大丈夫なの?」
「いいの心配しないで、あんたはそんなこと考えないでもっと違うことを考えて、、、、お父さんだって、仕事がまったく無い訳じゃないの。選んでるだけなの」
母が布団も敷かずに畳で寝ている父をゆすって起こした。父は噛み締めた歯をむき出しにして薄く片目を開けて、ゆっくりと手を伸ばしてコップに残った酒を一口で飲んだ。母が父の両目が開くまでまで待ってから言った。
「ねぇ、ユユが高校に行かないって言ってるの」
「おぉ、、、」
父はそう返事をして、腕を組んで真っ直ぐに何処かを見ていた。僕と母は父が話し出すのを待っていた。父が腕を下ろして胡座を組み直し僕の方を見て短く息を吸った。3秒後にその息はため息になって出てきて、父は酒をついだ。それを見た母がゆっくりと言った
「あんた、ユユを仕事に出していいの?」
なにも言わない父に母が続けて言った。
「あんた仕事に出てよ、毎日ごろごろしてるよりもあんただって、、、」
「うるせぇなー仕事がありゃ行ってらぁ、俺が売ってるのは家だっつこと、毎月ぽんぽん入ってくる仕事じゃぁねぇんだよ」
「のりおちゃんがハウスメーカーの仕事一緒に手伝わないかって言って、、、」
「んっなもんやるわきゃねーらに、俺がなんのために修行をしたと思ってるだぁ俺は親方だぞ、自分で引いた図面でしか仕事しねぇだよ。誰かの下で働くようなこんできるわきゃねーずらにぃ」
「じゃユユを働かせるの?」
「うるせぇ」
「手が空いてる今だけちょっと手伝いに行かせてもらえばいいでしょ?」
「黙れってんだよぉ、うんねん仕事して欲しけりゃ、おまんが仕事取ってこぉお」
父はコップをタンスに投げて壊し、立ち上がって大きな音を立てて歩き
「どこ行くの」
そう叫ぶ母の声を無視して釣竿を持って家を出ていった。次の日もその次の日も父は帰って来なかった。
10日後の朝、夏休みに入ったばかりの僕は、ドアが閉まる音で目が覚めた。まだ太陽は東の山の上で熱を出さずに光だけを放って、木や草に主役の時間を与えてる。網戸から差し込む光が僕の足元だけに当たっていた。隣に引いてある布団には姉はいない。姉は高校が夏休みになってからずっと帰って来ていない。その隣の布団にも母いなかった。台所から母の包丁の音が聞こえていた。まだ外から車の音もしない時間なのに父の声が聞こえた。10日ぶりに聞く父の声に僕は驚いて、ふすまの向こうから聞こえる会話に耳をすましていた。
「ベルトは?」
「はいはいここ」
「おいタオルと腹巻き」
「用意してあるよ」
「足袋出しとけ」
「はいはい」
父と母の会話がこんなに長く成立するのを初めて聞いた気がした。父はちちが高くて、やけに大きな声で母に話しかける。父の声が別人のようで今の父の顔が想像できなかった。父がふすまの向こうから僕を呼んだ
「おい、ユユ、おいぃい」
「やめなよ、起こさないであげてよ」
ふすまが開くと父が立っていた。タオルを頭に巻き、腹巻きをし、使い込まれた作業ズボンを履いて、髭を剃って髪を黒く染めていた。父の表情は柔らかくて、怖さがなくなっていた。髭を剃ったからなのか父が若く見えた。父が言った。
「仕事ついてくるか?」
「でも部活が、、、」
「いいだそんなもん、仕事ってもんを見に来い。」
父が僕の布団の上に腹巻きとタオルを置いて言った
「着替えろ」
「腹巻き?ダサくない?」
「それがいいんだよ」
そう言って父が笑った。姉にも見せてやりたかった父が笑った顔を。
僕と父が玄関に向かうと、母も後ろを付いてきて、父が玄関のドアを半分開けると
「いってらしゃい」
母がそう言った。母の声を聞いた父の動きが止まって、背中を向けたまま母に言う。
「ゆか、、、」
「はい」
「今日は上棟(じょうとう)だ」
「気を付けてね」
「はいよ」
父は背中を向けたままそう言った。
「いってらしゃい」
そう言いて母が父に頭をさげた。父が玄関を出ていって僕は急いで後を追って玄関を出た。二人で足袋を履いて団地の階段を降りていた。まだ6時前の階段は静かで、開けっぱなしの玄関ドアの向こうからイビキが聞こえた。団地の前の道にとめてある車に父が乗り込んだ、車がセルシオではなく汚い軽自動車に変わっていた。黒い2ドアの軽自動車は塗装が焼けていて所々白くなっていた。車のドアを開けるとギーと音を立てた。エアコンは使えなくて、車がマンホールを踏む度に、ガシャン、ギー、ガタガタ、と所々から音とほこりが飛び交う。坂道になれば隣の原付バイクに追い越された。ガソリンスタンドによった際は、若い女性スタッフさんの目線が痛くて僕は寝たふりをしてやり過ごした。車はのろのろと1時間ほど山を登り八ヶ岳の清里スキー場の近くまで来た。別荘地よりも上の土地、標高は1100メートルを越える森の中、細い道からもっと細い道に入る、
両脇に生えた木が空をおおって木のトンネルになっていた。少し進むと、そこだけ木が切られた、開けた場所に出た。
「付いたぞ」
父にそう言われ車を降りて道の南側を見た。八ヶ岳の裾の下に甲府盆地が小さな黒い水溜まりのように見え、一つ山の向こうから富士さんが甲府盆地を覗きこむようにそびえていた。道をはさんで北側には緩やかな傾斜の20メートルほど上に現場があった。その現場は在来工法で立っており棟上げ前で柱と梁と捨て床だけの状態、3階の梁の上は樽木も屋根束も無く屋根が無かった。僕は初めて家の骨組みを見た。縦の角材と横の角材が繋いであるだけで壁は一切なく、それはジャングルジムみたいだった。僕はこの棒の集まりが人の住む家になることが想像できなかった。僕は父に言った
「でかくない?」
「おぉ、地上3階地下1階で屋根に登れば5階ぐらいの高さになるぞ」
「マジで?他の大工さんは?」
「俺とお前だけだ」
「二人だけ?」
「ああ、昨日8人でバタバタ立てたけど、ここまでしかクレーンが届かなくてやめにしただ。」
「え?一人だけでこの家を立てるの?」
「まぁな」
「無理じゃない?」
「バカ、こんなプレカットの家なんてのは本当は俺がやる仕事じゃねぇんだよ、大工が作る家ってのはノミとノコギリで木を刻んで、カンナで仕上げて作るってもんなんだよ、こんな木を工場で削ってきて現場に運んでくるような家は、職人の魂がこもってないんだよ、積み木と一緒だ、俺が一人いればすぐに終らぁ」
父は怒っている訳じゃないのにその目には相槌も打たせない強い力がこもってた。でもこの家を一人で建てるなんて実現できない挑戦だと思った。
僕はなんとなくこの話題の居心地が悪くて話を変えた。
「セルシオどうしたの?」
「金に変えただ、、、うちの職人が外に出たからな、道具を買い換える金ぐらい持たせたくてな、、、お母さんには内緒だぞ」
僕が返事をするよりも先に1台の車が来て、一人の男が降りてきた。その男はシワの無いポロシャツにスラックスを履き、腹が出ていないスラリとした体、僕にはあ50代に見えた。父がその男にズボンのほこりを落としながら近付いて言った。
「おはようございます社長」
僕は父が敬語を使うのを初めて見た。僕はそんな父を見るのが、少し笑けて、少し痒くなった。社長が父に言う。
「おう、今日は二人だけ?」
「はい二人です」
「今日施主(家を買ったお客さん)が15時に来るけど、3時までに建て方終わる?」
「終わります」
社長が僕の方をまじまじ見て言った。
「えらい若い大工さんで」
「息子です」
「息子って、、、」
社長が父の方を見て言葉が止まった。父が社長の次の言葉を待たずに言う。
「ゆかの、、、」
社長が声を大きくして言う。
「おうおうそうか、おじちゃんの事覚えてるか?よく家の庭で一緒にBBQしただよ、覚ちゃいんかなぁ、ちっちゃかったからなぁ、、、」
「なんとなく覚えてますよ」
僕は覚えて無いのにそう言った。そうすると社長は大きく笑って僕の肩を叩き、言った。
「ほーかほーかじゃあ、今日はお父さんの仕事よーく覚えさせてもらえ。じゃあ15時にまた来るから、材料足りなかったらスタンドで電話借りて、じゃあよろしくな」
そう言って社長は現場から出ていった。父が僕に缶コーヒーを投げて
「一服してぼちぼちやらだぁ」
そうゆくりと独り言のように言いながら咥えたタバコに火を付けた。父が黙って現場を見ながらタバコをふかしていると、急にタバコを捨てて、
「おい、足袋の泥を落としとけ、飲み物持って上に上がるぞ。」
そう早口で言う父の声と顔つきは別の物になっていて、遠くを見ていた。トンカチを僕に渡して、返事も聞かないで足早に足場を登っていく。僕も父の後を追って3階の梁の高さの足場まで来た。高い、下から見た時よりも何倍も高く感じる。落っこちた時の想像ばかりしてしまう、こんなに地面が固そうに見えたのは初めてだった。梁の上に居る父が僕に言う
「なにやてるでぇて早く登ってこっちに来い」
父が僕を呼ぶ場所は梁の上、3寸5分(10センチ)の角材の上だ。4階の高さ
のジャングルジム、風が吹く空の中、手でつかまる物も無い、足場は10センチ、足の甲もはみ出る角材を踏み外せば、、、
「怖くて登れない」
僕は足を動かす事もできなかった。その場から動けない僕に父が言う
「じゃあ垂木を順番に並べろ」
僕は父が指さす4メートルの角材を両手で掴んだ、、、持ち上がらなかった、、、、僕はなにもできずにただ父の仕事を見ていた。
父は周りに生えた杉の木よりも高い場所で、僕が立つこともできない梁の上で、僕が持ち上げられない角材を振り回して、腹巻に刺したトンカチとくわえた釘で、八ヶ岳のその上まで突き抜ける音を響かせてた。右から左へ跳び回り、トンカチと鉛筆と定規、この小さな3つの道具だけで、みるみる屋根の形が出来ていく。汗に張り付いた木くずだらけの顔は、歯を食いしばり、見開いた眼は眉間にしわを作っていた。命を危険にさらして鬼のような顔をする父の動きは美しくて、父のトンカチが奏でる音は、鳥たちを歌わせているようだった。
僕は振り下ろす場所のないトンカチを握って、父の姿を見て思った、これが仕事なんだ。高校に行かないで仕事に出るなんて母に言ったが、僕は今日何もできずにいる。僕と父がいる場所は遠かった。時刻は19時を過ぎていた、セミも鳴くのを休みはじめ、森の色が全て吸い取られたように星だけが光ってる夜。足場にかけた投光器の前だけがオレンジに浮き上がっていた。父はオレンジの中で長い影を伸ばしてトンカチを振っていた。僕は立っているのが疲れて、車の隣で座っていた。下から見ると屋根に居る父は、月で餅をつくうさぎみたいだった。父が屋根の上から僕に叫ぶ。
「おい、早く屋根に登って来い。」
暗い足場をびくびくしながら登る僕に父がさっきよりも大きな声で言う
「なにやってるだ、早くしろ。」
僕が片面だけべニアが打ってある屋根を腰がひけた力ない足で一番上まで登ると、べニアに30cmほどの角材が二つ打ち付けてあった。父が投光器の明かりを消して片方の角材に
「特等席だ」
そう言った座った。僕も父を真似て座る。
「あっちを見てろ」
父がそう言って指をさした先は、下に広がる真っ黒の山肌だった。しばらくすると、山も雲も僕達も全てがピンク色になった。一発の花火が打ち上がって真っ黒の世界を自分の色に染めた。山の下で打ち上った花火は、甲府盆地に一輪のバラを生けたように見えた。始めて上から花火を見た、花火は上から見ても丸かった。僕は父に言った。
「花火ってどこから見てもキレイなんだ」
「そうだよ!!夜だからキレイなんだよ!!」
「なにが?」
「花火なんて昼間に見たら煙の塊ずら、だけんど花火をキレイって言ってる奴は夜を知ってる奴ってこんよ。」
「夜なんてみんな知ってるでしょ?」
「暗がりに入った事のねぇ奴だっていっぺー居るだ、だからお前は花火みたいな男になれし。いいかユユ、世の中を光で照らすような男になるように俺がお前に名前を付けたんだよ、だからお前は花火みてぇな男になれし」
「昼間は汚い男じゃん」
「太陽より光ってりゃいいら」
父はそう言って笑ってた、緑や紫に色を変えて、影を伸ばしたり縮めたりしながら。
この夏休みで僕の家は大きく変わっていった。
玄関のドアは開けられ、家の中に風が通るようになった。父は物を壊さなくなり、僕と姉は寝たフリをしなくなった。朝ご飯を僕と姉と父の3人で食べるようになり、姉が父に
「醤油とって」
そう言った。僕が団地の階段を登るのに覚悟が必要なくなった。そして、夏休みの間に妹が退院できることが分かった。僕は3日に一度ほど掃除を頼まれて父の現場に行った。父が一人で回す現場は、少しずつ仕上がっていき、妹に退院も少しずつ近づいてきた。妹が退院する前日、僕と姉の二人は部屋の飾り付けをしていた。千羽鶴の置き場所を姉と決めていると、父が急に帰ってきた。父は抱えていた任天堂のゲームキューブを僕に渡して
「この封筒をお母さんに渡しとけ」
そう言って口の閉じない封筒を僕にわたした。父が僕とお姉ちゃんの顔を交互に見てひとりごとのように言った。
「でかくなったな」
父は玄関の扉を閉めて出て行った。
この日から父はまた何処かに行ってしまった。
部活もあと少しで引退、義務教育の終わりが近づき、今のままの自分ではいられなくなる。名前の分からない不安と焦りに急かされながら、肌を焦がす太陽よりも暑く、興味と情熱が体を熱くして走らずにはいられない。使い道の分からない体力が無限に湧き出して、消せない熱に狂わされ、大きく笑って、大きく悩んで、大きく泣いていた。
土曜日の部活の帰り道、セミの声が空から降って、太陽の光を反射した田んぼが緑に光って眩しい。同級生の若尾ゆりと僕の二人は肩がくっつく距離で自転車を押してゆっくりと歩いてる。目の前の信号機の先はお互い別の道に別れて家に帰る。今は信号機が青だから二人はゆっくり歩いてる。僕とゆりは恋人同士なのか分からない。休みの日に二人だけで出かけた事もない、ただ土曜日の部活の帰り道を二人で歩くそれだけの関係だった。好きだなんて言った事も、言われた事もない。しかし学校に何人も女性がいるが僕のほっぺたに温度を与える女性はゆりだけだった。ゆりと話していると親も友達も自分も知らない僕が心の舵をきる。ゆりが僕の名前を呼ぶだけで言葉が止まって、授業中にゆりが先生に答えを求められると、僕も一緒に汗をかいた。きっと僕達二人は時間と共に関係を深めて、結婚して、子供を作って、同じ時間の中で歳をとるんだ、そんな未来が決まり事のように鮮明に見えていた。
今日僕は決めていた、二人の関係を前に進めようと。次の月曜日二人で一緒に学校に行こう、そうゆりに伝えようと決めていた。二人で登校すれば周りのみんなに僕達の関係が特別だとばれてしまう。ゆりが嫌だと言ったら、僕はどんな顔をすればいいのだろうか?僕の中に流れる特別な気持ちはゆりの中にも流れているのだろうか?ゆりに一緒に登校しようと伝えるのは怖かった、しかし部活の引退が近づき、二人だけで帰れる土曜日はもう数回しか来ない。だから今日伝えようと覚悟を決めたのに、ゆいの話に相槌しか打てずにいる。 信号の色が赤に変わって僕達は立ち止まる。この信号が青になれば二人だけで話せるのは次の土曜日だ。ゆりの会話を止める“あのさ“が僕の渇いた口からずっと出て来ない。きっと信号はすぐに変わる、だから今ゆりの話を遮ってしまおう、そう決心してゆりの話を聞いていた。
「ほんとに最悪なんだよ、私もうお父さんと口きかない、だってさ、私の誕生日のプレゼントはシベリアンハスキーがいいってずっと言ってたの。それで誕生日の日にお父さんがハスキー犬を買って家に連れてきたの。初めて見たハスキーがすっごい可愛かったんだけど、首輪にゴン太って書いてあって、お父さん私の犬に勝手に名前つけてたの、ありえなくない?私ペットにはラッキーって名前つけるって決めてたの、それなのにゴン太って意味わかんない、マジで私お父さんの事嫌いになっちゃって二日口聞いてないんだよね、本当にムカつかない?ねぇ聞いてるの?」
ゆりの話が終わって、部屋の電気を急につけられた気持ちだった。僕の口から考えるよりも早く言葉が出た。
「愛されてるじゃん」
その言葉を聞いてゆりが大きく笑って言った。
「今そーいう話じゃないじゃん、ユユってすぐにボケるから会話になんないよ。」
「それってムカつく話?」
「ムカつくって言ってるんじゃん、ねぇ話聞いてたの?」
きゅうに部屋の灯りをつけられた、僕が話している相手は鏡だったんだ。ずっと見えないフリをしていた、一生懸命に手繰り寄せていた紐の先には何もついていなかった。僕がしているのは恋愛なんかじゃなくて妄想だった。その事に今気がついて僕は叫びたい気持ちを飲み込んで、震える唇で言った。
「俺何があっても親を嫌いなんて言えないよ。」
「急になんの話?」
「なんかゆりと話してると痛いんだよ。」
「なんで泣いてるの?」
ゆりに言われて初めて自分が泣いてる事に気がついた、気がついた時にはもう涙は止められなくて、こんな顔をゆりに見られるのが恥ずかしくて僕は信号が赤なのに交差点を渡ろうとした、そんな僕の服を掴んでゆりが叫ぶ。
「行かないで、」
「やめて」
「どうしちゃったの?急になに?こんな感じでバイバイしたくない」
僕はゆりの聞いたことのない声に驚いて立ち止まった。喉を裂かれたような声を聞いて罪悪感と心配が僕の言葉を奪う。ゆりが下を向いてセーラー服の裾を両手で握りしめて、セーラー服と同じぐらいシワのよった顔で話だす。
「分かんない私、、、ユユ自分の話しないし、いつも私ばっかり話してる、、、分かんないよ、なんで優しいの?なんで私と一緒にいるの?ユユ私のこと好きなの?」
「好きだよ、愛してるんだと思う、、ゆりと結婚したいって考えてた、、、」
「、、、じゃあなんで泣いてるの?」
「ゆりの話を聞いてると、怖いんだよ」
「分かんない、いつもユユが分かんない。」
「俺も分かんないよ。」
「これお母さんがユユのために買ってくれたやつ。ずっと恥ずかしくて渡せなかった、、、これあげる」
ゆりが渡したのは必勝って刺繍がしてある踵のサポーターだった。僕が剣道部の練習で痛めた踵のことをゆりはどこかで知って、心配をしてくれていたんだ。僕はずっと欲しかったサポーターを強引にゆりの自転車のカゴに入れて叫んだ。自分では抑えられない熱と音を出すように。
「いらねーよ、こーゆーのが嫌なんだよ、、、こんなに違うのかよ」
「どうして、、、、」
触れるのも怖いほど大切なゆりの表情が壊れた。僕は自転車に乗った。ゆりは何も言わなかった。出口を塞いだ怒りと、恐怖と、悲しさ、罪が自転車のペダルを踏み下す。考えることを放棄して一心不乱に自転車を漕いだ。すごいスピードで。考える事を放棄したから写真のようにゆりの表情が頭に張り付く。その写真を剥がすように自転車を漕いだ。そごいスピードで。助けが欲しくて何か歌を歌おうとしたが、嵐や大塚愛思い付くのはゆりの好きな曲がかりだった。気がつけば僕は止まってしまいそうな自転車をふらつきながらゆっくりと漕いでいた。
団地の駐輪場に自転車を止めて、団地の階段を登る。1階も2階も3階もどの家も玄関のドアをあけて家の中に風を通していた。僕は4階にある自分の家の前に立って呼吸を整えた。青いペンキが剥げて、所々が錆びた重たい鉄のドアを恐る恐る開けて、音がしないようにゆっくりと閉める。まだ16時なのに暗い玄関でそっと靴を脱ぐ。
「靴履いたまま入りな」
僕は背中で聞いた小さな小さなかすれた声にびくついて急いで振り返った。そこには姉がいた。僕は姉の顔を見て少し安心して促されるまま靴を履いて玄関を上がる。廊下には、割れたガラスのコップと壊れた扇風機の部品が散らばっていた。何がおきたのかは想像できる、でも想像はしないようにした。
僕と姉は二人で寝室に入った。しっきっぱなしの3枚の布団。まだ太陽が沈んでいないのに、僕と姉は隣に並んで布団に入る。夏なのに顔まで布団をかぶって寝たふりをした。あと少し、あと少しすれば布団から出られる、だから僕と姉は二人で寝たふりをしていた。すこしすると寝室のふすまがピシャンっと大きな音を立てて開いた。
「おい、ユユおまん帰ってきたずら?こっち来て一緒に酒でも飲め」
そう言って部屋に父が入って来た。父はひどく酔っぱらっていて真っ赤な顔で目が座っていた。寝癖だらけの茶髪に伸ばしっぱなしの髭、上裸に白なのか灰色なのか分からないジーパン姿。父はもう半年仕事をしていない。
ハウスメーカーが山梨にも入ってきて、父が親方をしている工務店で残っているのは父だけだった。毎日父は朝起きて黙ってテレビの前で積み木をぼーといじってる。その積み木は、病室から出られない妹のために木を触らせたいと祖父が作った積み木で、妹が飽きて手放した物だった。父はその積み木を積んでは崩していた。家から出ずに朝から酒を飲んで、夜を待たずに酔い疲れて寝る。借金を抱えて、彼女と別れて、家に帰ってきてそんな毎日を半年続けていた。父はベロベロになるまで言葉を口にしなかった。ずっと家族に背中を向けて黙って酒を飲み、急に物を壊す。そんな父の背中を僕は見れなかった。なにかの理由を探して酒を飲む。理由がないと寝むる場所もなくて、理由がないとプライドを守れなくて、理由がないと家族とも話せない。酒を飲む父の背中は、なにかにひっしだった。枯れそうな花に酒を飲ませる父を、僕は見れなかった。
「おい、ユユおまん帰ってきたずら?こっち来て一緒に酒でも飲め」
そう言って父が寝室に入ってきた。僕と姉は布団を顔までかぶって寝たふりをしていた。あと2時間もすれば父は酔い疲れて眠ってしまう、それまでの我慢だった。
「おい、聞いてんのか?」
怒鳴る父は寝たふりををする僕の髪の毛をつかんで、草むしりみたいに、すごい力で僕を引っ張り上げた。僕は痛くて甲高い声になりながら父に言う。
「痛い、やめて、部活で疲れてるの、寝かせて。」
「なんだぁ?こっち来りゃぁいいじゃんか?」
「やだ」
「んだぁバカが」
父がそう言って僕の髪の毛を離し、枕元に置いてあった時計を投げて壊した。家族の写真がはめこんである時計を。姉は布団をかぶって声を出さずに泣いていた。これが僕の日常、なにも特別ではない。最近家に帰って来ない姉、居場所の無い父、寝顔しか見ない母、白血病で家にいない妹、これが僕の日常、なにも特別ではない、明日も続く日常。
僕は壊れた時計を拾ってゆりの事を考えてた。ゆり、あなたの愚痴を聞いていると痛いんだよ、自分が幸せじゃないって言われているようで。美しくて優しい君に見せたくなかったんだ自分を。重ならなかったんだ二人が。
次の日の日曜日の朝、母が夜勤のパートから帰ってきて朝ご飯の支度をしていた。父と姉は寝ている。まだ活動を始めていない静かな日曜日の朝、こんな朝早くに起きてくる僕を不思議そうに見ながら母が言った。
「はやいじゃん、部活の試合でもあるの?」
僕はずっと言おうか悩んでいたことを言った。
「俺、高校行かないで働くよ」
「働くって、、、なにかやりたいことでもあるの?」
働きたい訳ではなかった。しかしもうこの道しか無いってうすうす気が付いていた。僕が働けば母に楽をさせてあげられる、それにゆりとあんな別れかたをしてもう学校生活に憧れも未練も無くなった。子供の頃からずっと父が帰って来れば幸せになるって思ってた、でもこの半年間ずっと僕は布団をかぶって隠れてた。父が呑んだくれるのも時間がたてば解決すると思ってた、でも助けになんて誰も来なかった。笑いたいときにはいつも回りに人が集まって、泣きたいときは誰も来ない。先生だって友達だってゆりだって泣きたいときにはいつも来ない。ゆりに告白できなかかったのがこの家のせいなら、父も母も姉も妹も、みんな一人になってるんじゃないのか?僕が働けば家族が少しでも笑うんじゃないのか?誰も助けに来ないのなら僕が家族を助ければいいじゃんか。だから僕は母に言った。
「俺が働かないと、どうにもならないだろ、、、妹が帰ってきたらどうするの?帰りたいかここに?」
「そんなこと考えないでいいの」
「そんなことって、、、」
「大丈夫、お母さん昼も働くから、そんなに心配することじゃない」
「そんなに働いたら死んじゃうよ、、、俺が働けば少しはましになるでしょ」
「いいの、あんたは部活の引退も近いでしょ?今はそれに集中してな。家の事は考えなくていいから」
「考えるよ、考えるだろ、お父さんが壊した炊飯器を買い換えられなくて土鍋でご飯炊いてるんだよ、あんが帰ってきたら来年は中学生だよ、部活やるのにだってお金かかるよ。」
「大丈夫だから、」
「なにが大丈夫なの?」
「いいの心配しないで、あんたはそんなこと考えないでもっと違うことを考えて、、、、お父さんだって、仕事がまったく無い訳じゃないの。選んでるだけなの」
母が布団も敷かずに畳で寝ている父をゆすって起こした。父は噛み締めた歯をむき出しにして薄く片目を開けて、ゆっくりと手を伸ばしてコップに残った酒を一口で飲んだ。母が父の両目が開くまでまで待ってから言った。
「ねぇ、ユユが高校に行かないって言ってるの」
「おぉ、、、」
父はそう返事をして、腕を組んで真っ直ぐに何処かを見ていた。僕と母は父が話し出すのを待っていた。父が腕を下ろして胡座を組み直し僕の方を見て短く息を吸った。3秒後にその息はため息になって出てきて、父は酒をついだ。それを見た母がゆっくりと言った
「あんた、ユユを仕事に出していいの?」
なにも言わない父に母が続けて言った。
「あんた仕事に出てよ、毎日ごろごろしてるよりもあんただって、、、」
「うるせぇなー仕事がありゃ行ってらぁ、俺が売ってるのは家だっつこと、毎月ぽんぽん入ってくる仕事じゃぁねぇんだよ」
「のりおちゃんがハウスメーカーの仕事一緒に手伝わないかって言って、、、」
「んっなもんやるわきゃねーらに、俺がなんのために修行をしたと思ってるだぁ俺は親方だぞ、自分で引いた図面でしか仕事しねぇだよ。誰かの下で働くようなこんできるわきゃねーずらにぃ」
「じゃユユを働かせるの?」
「うるせぇ」
「手が空いてる今だけちょっと手伝いに行かせてもらえばいいでしょ?」
「黙れってんだよぉ、うんねん仕事して欲しけりゃ、おまんが仕事取ってこぉお」
父はコップをタンスに投げて壊し、立ち上がって大きな音を立てて歩き
「どこ行くの」
そう叫ぶ母の声を無視して釣竿を持って家を出ていった。次の日もその次の日も父は帰って来なかった。
10日後の朝、夏休みに入ったばかりの僕は、ドアが閉まる音で目が覚めた。まだ太陽は東の山の上で熱を出さずに光だけを放って、木や草に主役の時間を与えてる。網戸から差し込む光が僕の足元だけに当たっていた。隣に引いてある布団には姉はいない。姉は高校が夏休みになってからずっと帰って来ていない。その隣の布団にも母いなかった。台所から母の包丁の音が聞こえていた。まだ外から車の音もしない時間なのに父の声が聞こえた。10日ぶりに聞く父の声に僕は驚いて、ふすまの向こうから聞こえる会話に耳をすましていた。
「ベルトは?」
「はいはいここ」
「おいタオルと腹巻き」
「用意してあるよ」
「足袋出しとけ」
「はいはい」
父と母の会話がこんなに長く成立するのを初めて聞いた気がした。父はちちが高くて、やけに大きな声で母に話しかける。父の声が別人のようで今の父の顔が想像できなかった。父がふすまの向こうから僕を呼んだ
「おい、ユユ、おいぃい」
「やめなよ、起こさないであげてよ」
ふすまが開くと父が立っていた。タオルを頭に巻き、腹巻きをし、使い込まれた作業ズボンを履いて、髭を剃って髪を黒く染めていた。父の表情は柔らかくて、怖さがなくなっていた。髭を剃ったからなのか父が若く見えた。父が言った。
「仕事ついてくるか?」
「でも部活が、、、」
「いいだそんなもん、仕事ってもんを見に来い。」
父が僕の布団の上に腹巻きとタオルを置いて言った
「着替えろ」
「腹巻き?ダサくない?」
「それがいいんだよ」
そう言って父が笑った。姉にも見せてやりたかった父が笑った顔を。
僕と父が玄関に向かうと、母も後ろを付いてきて、父が玄関のドアを半分開けると
「いってらしゃい」
母がそう言った。母の声を聞いた父の動きが止まって、背中を向けたまま母に言う。
「ゆか、、、」
「はい」
「今日は上棟(じょうとう)だ」
「気を付けてね」
「はいよ」
父は背中を向けたままそう言った。
「いってらしゃい」
そう言いて母が父に頭をさげた。父が玄関を出ていって僕は急いで後を追って玄関を出た。二人で足袋を履いて団地の階段を降りていた。まだ6時前の階段は静かで、開けっぱなしの玄関ドアの向こうからイビキが聞こえた。団地の前の道にとめてある車に父が乗り込んだ、車がセルシオではなく汚い軽自動車に変わっていた。黒い2ドアの軽自動車は塗装が焼けていて所々白くなっていた。車のドアを開けるとギーと音を立てた。エアコンは使えなくて、車がマンホールを踏む度に、ガシャン、ギー、ガタガタ、と所々から音とほこりが飛び交う。坂道になれば隣の原付バイクに追い越された。ガソリンスタンドによった際は、若い女性スタッフさんの目線が痛くて僕は寝たふりをしてやり過ごした。車はのろのろと1時間ほど山を登り八ヶ岳の清里スキー場の近くまで来た。別荘地よりも上の土地、標高は1100メートルを越える森の中、細い道からもっと細い道に入る、
両脇に生えた木が空をおおって木のトンネルになっていた。少し進むと、そこだけ木が切られた、開けた場所に出た。
「付いたぞ」
父にそう言われ車を降りて道の南側を見た。八ヶ岳の裾の下に甲府盆地が小さな黒い水溜まりのように見え、一つ山の向こうから富士さんが甲府盆地を覗きこむようにそびえていた。道をはさんで北側には緩やかな傾斜の20メートルほど上に現場があった。その現場は在来工法で立っており棟上げ前で柱と梁と捨て床だけの状態、3階の梁の上は樽木も屋根束も無く屋根が無かった。僕は初めて家の骨組みを見た。縦の角材と横の角材が繋いであるだけで壁は一切なく、それはジャングルジムみたいだった。僕はこの棒の集まりが人の住む家になることが想像できなかった。僕は父に言った
「でかくない?」
「おぉ、地上3階地下1階で屋根に登れば5階ぐらいの高さになるぞ」
「マジで?他の大工さんは?」
「俺とお前だけだ」
「二人だけ?」
「ああ、昨日8人でバタバタ立てたけど、ここまでしかクレーンが届かなくてやめにしただ。」
「え?一人だけでこの家を立てるの?」
「まぁな」
「無理じゃない?」
「バカ、こんなプレカットの家なんてのは本当は俺がやる仕事じゃねぇんだよ、大工が作る家ってのはノミとノコギリで木を刻んで、カンナで仕上げて作るってもんなんだよ、こんな木を工場で削ってきて現場に運んでくるような家は、職人の魂がこもってないんだよ、積み木と一緒だ、俺が一人いればすぐに終らぁ」
父は怒っている訳じゃないのにその目には相槌も打たせない強い力がこもってた。でもこの家を一人で建てるなんて実現できない挑戦だと思った。
僕はなんとなくこの話題の居心地が悪くて話を変えた。
「セルシオどうしたの?」
「金に変えただ、、、うちの職人が外に出たからな、道具を買い換える金ぐらい持たせたくてな、、、お母さんには内緒だぞ」
僕が返事をするよりも先に1台の車が来て、一人の男が降りてきた。その男はシワの無いポロシャツにスラックスを履き、腹が出ていないスラリとした体、僕にはあ50代に見えた。父がその男にズボンのほこりを落としながら近付いて言った。
「おはようございます社長」
僕は父が敬語を使うのを初めて見た。僕はそんな父を見るのが、少し笑けて、少し痒くなった。社長が父に言う。
「おう、今日は二人だけ?」
「はい二人です」
「今日施主(家を買ったお客さん)が15時に来るけど、3時までに建て方終わる?」
「終わります」
社長が僕の方をまじまじ見て言った。
「えらい若い大工さんで」
「息子です」
「息子って、、、」
社長が父の方を見て言葉が止まった。父が社長の次の言葉を待たずに言う。
「ゆかの、、、」
社長が声を大きくして言う。
「おうおうそうか、おじちゃんの事覚えてるか?よく家の庭で一緒にBBQしただよ、覚ちゃいんかなぁ、ちっちゃかったからなぁ、、、」
「なんとなく覚えてますよ」
僕は覚えて無いのにそう言った。そうすると社長は大きく笑って僕の肩を叩き、言った。
「ほーかほーかじゃあ、今日はお父さんの仕事よーく覚えさせてもらえ。じゃあ15時にまた来るから、材料足りなかったらスタンドで電話借りて、じゃあよろしくな」
そう言って社長は現場から出ていった。父が僕に缶コーヒーを投げて
「一服してぼちぼちやらだぁ」
そうゆくりと独り言のように言いながら咥えたタバコに火を付けた。父が黙って現場を見ながらタバコをふかしていると、急にタバコを捨てて、
「おい、足袋の泥を落としとけ、飲み物持って上に上がるぞ。」
そう早口で言う父の声と顔つきは別の物になっていて、遠くを見ていた。トンカチを僕に渡して、返事も聞かないで足早に足場を登っていく。僕も父の後を追って3階の梁の高さの足場まで来た。高い、下から見た時よりも何倍も高く感じる。落っこちた時の想像ばかりしてしまう、こんなに地面が固そうに見えたのは初めてだった。梁の上に居る父が僕に言う
「なにやてるでぇて早く登ってこっちに来い」
父が僕を呼ぶ場所は梁の上、3寸5分(10センチ)の角材の上だ。4階の高さ
のジャングルジム、風が吹く空の中、手でつかまる物も無い、足場は10センチ、足の甲もはみ出る角材を踏み外せば、、、
「怖くて登れない」
僕は足を動かす事もできなかった。その場から動けない僕に父が言う
「じゃあ垂木を順番に並べろ」
僕は父が指さす4メートルの角材を両手で掴んだ、、、持ち上がらなかった、、、、僕はなにもできずにただ父の仕事を見ていた。
父は周りに生えた杉の木よりも高い場所で、僕が立つこともできない梁の上で、僕が持ち上げられない角材を振り回して、腹巻に刺したトンカチとくわえた釘で、八ヶ岳のその上まで突き抜ける音を響かせてた。右から左へ跳び回り、トンカチと鉛筆と定規、この小さな3つの道具だけで、みるみる屋根の形が出来ていく。汗に張り付いた木くずだらけの顔は、歯を食いしばり、見開いた眼は眉間にしわを作っていた。命を危険にさらして鬼のような顔をする父の動きは美しくて、父のトンカチが奏でる音は、鳥たちを歌わせているようだった。
僕は振り下ろす場所のないトンカチを握って、父の姿を見て思った、これが仕事なんだ。高校に行かないで仕事に出るなんて母に言ったが、僕は今日何もできずにいる。僕と父がいる場所は遠かった。時刻は19時を過ぎていた、セミも鳴くのを休みはじめ、森の色が全て吸い取られたように星だけが光ってる夜。足場にかけた投光器の前だけがオレンジに浮き上がっていた。父はオレンジの中で長い影を伸ばしてトンカチを振っていた。僕は立っているのが疲れて、車の隣で座っていた。下から見ると屋根に居る父は、月で餅をつくうさぎみたいだった。父が屋根の上から僕に叫ぶ。
「おい、早く屋根に登って来い。」
暗い足場をびくびくしながら登る僕に父がさっきよりも大きな声で言う
「なにやってるだ、早くしろ。」
僕が片面だけべニアが打ってある屋根を腰がひけた力ない足で一番上まで登ると、べニアに30cmほどの角材が二つ打ち付けてあった。父が投光器の明かりを消して片方の角材に
「特等席だ」
そう言った座った。僕も父を真似て座る。
「あっちを見てろ」
父がそう言って指をさした先は、下に広がる真っ黒の山肌だった。しばらくすると、山も雲も僕達も全てがピンク色になった。一発の花火が打ち上がって真っ黒の世界を自分の色に染めた。山の下で打ち上った花火は、甲府盆地に一輪のバラを生けたように見えた。始めて上から花火を見た、花火は上から見ても丸かった。僕は父に言った。
「花火ってどこから見てもキレイなんだ」
「そうだよ!!夜だからキレイなんだよ!!」
「なにが?」
「花火なんて昼間に見たら煙の塊ずら、だけんど花火をキレイって言ってる奴は夜を知ってる奴ってこんよ。」
「夜なんてみんな知ってるでしょ?」
「暗がりに入った事のねぇ奴だっていっぺー居るだ、だからお前は花火みたいな男になれし。いいかユユ、世の中を光で照らすような男になるように俺がお前に名前を付けたんだよ、だからお前は花火みてぇな男になれし」
「昼間は汚い男じゃん」
「太陽より光ってりゃいいら」
父はそう言って笑ってた、緑や紫に色を変えて、影を伸ばしたり縮めたりしながら。
この夏休みで僕の家は大きく変わっていった。
玄関のドアは開けられ、家の中に風が通るようになった。父は物を壊さなくなり、僕と姉は寝たフリをしなくなった。朝ご飯を僕と姉と父の3人で食べるようになり、姉が父に
「醤油とって」
そう言った。僕が団地の階段を登るのに覚悟が必要なくなった。そして、夏休みの間に妹が退院できることが分かった。僕は3日に一度ほど掃除を頼まれて父の現場に行った。父が一人で回す現場は、少しずつ仕上がっていき、妹に退院も少しずつ近づいてきた。妹が退院する前日、僕と姉の二人は部屋の飾り付けをしていた。千羽鶴の置き場所を姉と決めていると、父が急に帰ってきた。父は抱えていた任天堂のゲームキューブを僕に渡して
「この封筒をお母さんに渡しとけ」
そう言って口の閉じない封筒を僕にわたした。父が僕とお姉ちゃんの顔を交互に見てひとりごとのように言った。
「でかくなったな」
父は玄関の扉を閉めて出て行った。
この日から父はまた何処かに行ってしまった。
最新写メ日記
月別アーカイブ
全在籍セラピスト最新写メ日記
秘密基地グループ
-
東京エリア
東京秘密基地本店 渋谷秘密基地 新宿秘密基地 池袋秘密基地 立川秘密基地 上野秘密基地 品川秘密基地 錦糸町秘密基地 八王子秘密基地 町田秘密基地 六本木秘密基地 銀座秘密基地 青山秘密基地 世田谷秘密基地 赤坂秘密基地 吉祥寺秘密基地 恵比寿秘密基地 赤羽秘密基地 西麻布秘密基地 新大久保秘密基地 中野秘密基地 -
関東エリア
横浜秘密基地 千葉秘密基地 さいたま秘密基地 宇都宮秘密基地 川崎秘密基地 群馬秘密基地 西川口秘密基地 湘南秘密基地 茨城秘密基地 船橋秘密基地 大宮秘密基地 柏秘密基地 松戸秘密基地 水戸秘密基地 舞浜秘密基地 越谷秘密基地準備中 -
北海道・東北エリア
札幌秘密基地 仙台秘密基地 郡山秘密基地 山形秘密基地 岩手秘密基地 青森秘密基地募集中 秋田秘密基地募集中 -
北陸・甲信越エリア
新潟秘密基地 長野秘密基地 甲府秘密基地 金沢秘密基地募集中 富山秘密基地募集中 福井秘密基地募集中 -
東海エリア
静岡秘密基地 名古屋秘密基地 三重秘密基地 岐阜秘密基地 浜松秘密基地 岡崎秘密基地 豊橋秘密基地 藤が丘秘密基地 -
関西エリア
大阪秘密基地 神戸秘密基地 なんば秘密基地 京都秘密基地 梅田秘密基地 堺東秘密基地 京橋秘密基地 滋賀秘密基地募集中 奈良秘密基地募集中 和歌山秘密基地募集中 -
中国エリア
広島秘密基地 岡山秘密基地 山口秘密基地 出雲秘密基地募集中 鳥取秘密基地募集中 -
四国エリア
香川秘密基地 徳島秘密基地 高知秘密基地募集中 松山秘密基地募集中 -
九州・沖縄エリア
博多秘密基地 沖縄秘密基地 鹿児島秘密基地 大分秘密基地 北九州秘密基地 宮崎秘密基地 佐賀秘密基地 熊本秘密基地 長崎秘密基地 中洲秘密基地 久留米秘密基地募集中