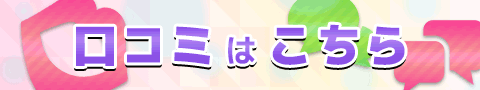6/4 15:10 UP! 愛されてる YUYU(ユユ)(29)
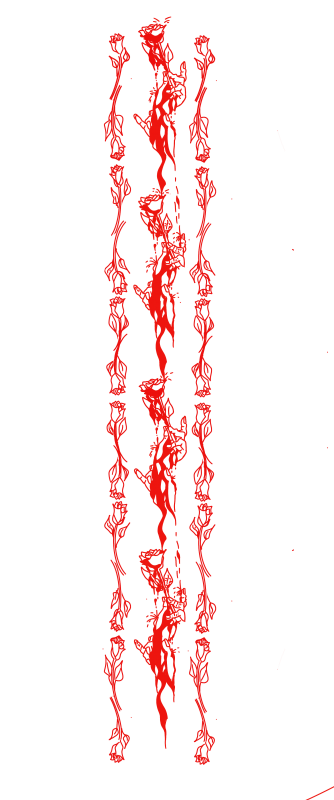
僕の世界の外からその車はきた。僕が友達と歩いている少し先にその車はハザードランプを焚いて道を塞ぐように停車した。車が1台しか通れない細い道の両脇には、まだ稲を植えていない水を貼った田んぼが遠くまで続いている。田んぼの水面に空が反射して、この道の上と下の両方に空があるようだった。この道の下の雲と上の雲、そのどちらよりもその車は白く光っていた。梅雨入り前の風邪は軽くて透明で僕の張り付いた汗を冷やす。頭の中はジンジンと熱いのに、顔の表面は冷たい。この道を進めば、昨日と同じ夜はもう来ない、この車がこの世界から僕を連れ出してくれるんだ。今すぐに走り出して車に飛び乗りたかった、ずっと待っていた、ずっと待っていた時間が突然来た、そう思うと緊張して足が前に出ない。一緒に登校している友達たちが車を指さして言った。
「あの車ベンツだ」
「ベンツってなに?」
「金持ちの車だよ」
「どんぐらい金持ちの車?」
「すげ〜金持ちの車だよ!!どんな人が乗ってるのかな?見に行こうぜ。」
そうはしゃいでいた友達数人が“バタン“っとドアの閉まる音と同時に言葉を飲み込んだ。車から降りた大男がこっちに向かって歩いていた。運転手の男は40代前半で、薄い革ジャンにギンガムチェックのシャツ、ワンウォッシュデニムにチェルシーブーツ、そのコーディネイトの邪魔をするように大きなネックレスと指輪が金色に光っていた。細い目に吊り上がった眉毛、その顔は柔らかい場所なんて無くて、この場所に笑顔が作られるなんて想像できなかった。その運転手の顔を見て友達が言う。
「逃げる?」
僕が答えるのを待たずにみんな逃げようとしていた。そんな僕に運転手の男が低くてよく通る声で言った。
「ユユ」
友達が怯えた声で僕に言った。
「誰?」
「お父さん」
「ユユのお父さん、、、え?じゃあ車の中見せてもらえるのかな?」
「今度ね、先に学校行ってて」
友達たちは走り出し、ドタドタと道の先に消えてしまった。
僕はお父さんが帰ってくるのをずっと待っていた。僕の家は、母さんのパートのお金で母、姉、妹、僕の四人で生活していた。お金に余裕がなくて、借金取りの電話がうるさくて家の電話線はずっと抜いたままだった。お母さんはよく隠れて泣いていた。妹は病気で何年も帰って来ない。僕は毎日おねいちゃんと二人だけで食事をする。でもそんな事は全部へっちゃらだった。全部お父さんが帰って来れば可決するから。お母さんがいつも僕に言っていたんだ、
「お父さんは大工の仕事が忙しくて帰って来ないんだよ」
だからお父さんが帰って来る日は、いっぱい貯めたお金を持って帰ってきて、お母さんが働きに出なくなって、妹にいい薬を飲ましてあげて、家族がみんな揃って食事ができる日になるんだ。サザエさんを見るたびに憧れた、家族がみんな揃っている食事、あの憧れの食事が僕の家にも来るんだ。僕の知らない世界で家族のために一人で仕事をしているお父さん、あの白いピカピカの車いっぱいに幸せを乗せて迎えにきたんだ。
僕はお父さんの後をついていき、お父さんが車のドアを開けた、そこには男の子とキレイなオバサンが乗っていた。僕はこの町でスカートを履いているオバサンを始めて見た。白とピンクの花柄のスカートは薄い生地で服の上から少し太ももの形がわかった。黒くて細い髪は艶やかで、猫のように見開いた瞳に真横に伸びた眉毛が子供のようで、僕は、キレイなまま歳を取った女の人を始めて見た。急な知らない人の登場で驚き、黙ったままの僕にお父さんが言う。
「富士急ハイランドに行くぞ」
「今日、学校だよ」
「学校には連絡するから大丈夫だ、 休みの日は混んでるから今日行くんだよ。」
「お母さんは知ってるの?」
「知ってる。いいから行くぞ」
お父さんの声が少し大きくなり、僕が怖がるよりも前にキレイなオバサンが助手席から身を乗り出して
「富士急ハイランド行くぞーー」
そう言って手のひらを前に出して、僕とハイタッチをすると、
「かわいいー」
そう言って笑った。
男の子は僕よりも1歳か2歳年下で、車に乗った僕の方を見ることもなく、ぶつぶつと何かを話しながらゲームボーイアドバンスをプレイしていた。僕が黙っているとバックミラー越しにお父さんと目があって、すぐに恥ずかしくてなって僕が目を逸らすと、お父さんが僕に言った。
「お前もゲーム欲しいか?買ってやりゃー二人でできるもんな。」
「いらない」
僕はすぐに答えた、僕だけ遊園地に来て、ゲームまで買ってもらったら、妹と姉ちゃんに申し訳がないから。僕の答えを聞いて、お父さんが少し暗い顔になった。
盛り上がっていないのにしりとりをずっと続けながら僕たちは富士急ハイランドに着いた。お化け屋敷をリニューアルしたばかりの園内は、平日なのに人でごった返していた。
入り口のゲートを走って潜ろうとする男の子にキレイなオバサンが大きな声で言う。
「迷子になるから手を繋いでぇーー」
男の子はお土産屋さんの方を指さし、僕のお父さんの手を掴んで言った。
「パパー僕あれ欲しい」
僕は心の中で呟いた。そっか、お父さんはここに居たんだ、、、僕の知らない世界ってここだったんだ。お姉ちゃんがブランコから落ちて顔を怪我した日も、妹が入院した日も、骨折したお母さんに変わって、僕とお姉ちゃんが新聞配達をしていた日も、お父さんはここに居たんだ。何も言わない僕の姿を、お父さんが男の子に腕を引かれながら見た。僕は必死に表情を変えないように努力していた。自分が努力していたから分かった、お父さんも、オバサンも、同じ努力をしていた。このときの僕は、怒りや、悲しみなんて感じている余裕はなかった。きっとこの男の子よりもかわいい子供になれば、お父さんは帰ってくる、そう思ったから。お姉ちゃんに、妹に、お母さん、みんなまだお父さんが必要なんだ、僕は頑張って、連れてきてもらった遊園地を楽しんでいるように見せようとした。でも僕は、お父さんに話しかける事もできずに、ただお父さんの顔を見てお父さんが何を考えているのか探っているだけだった。本当は探っているのではなく、まだ僕のことを嫌いになってはいないか、答え合わせをしていた。そんな僕とは違って、男の子は
「パパ次はあれに乗ろうよ。パパ、○○君はこの前あのジェットコースーターに一人で乗ったんだよ。ねぇパパ見てぇ」
楽しそうで、かわいい子供だった。僕は心の中で呟いた、やっぱりあんなかわいい子供がいる家には帰りたくなるんだろうな、そう自分で呟いたのに、なんだか他人に言われているように感じて、急に悲しくなってきた。男の子にこの暗い顔を見られたくなくて僕は一番後ろを歩いていた、男の子と、お父さんがジェットコースターを乗りに行こうと僕を誘ったが、僕は怖いからとオバサンとベンチで待っている事にした。
オバサンが僕にチェロスを買ってくれた。人生で初めて食べるチェロスは、よくお母さんが作ってくれる、パンの耳を油で揚げたお菓子のような味がした。同じような味だが僕はお母さんが油で揚げたパンの耳の方が好きだった。黙ってチェロスを食べる僕にオバサンが優しい声で言った。
「ユユ君は遊園地あんまり好きじゃ無かったかな?」
「一人だから」
「そっかぁ、じゃぁ私とあの子といっぱい会って、少しずつ友達になったら楽しくなるかな?」
「わかんない」
「じゃあ次はユユ君のいきたいところに行こうね。どこに行きたい?」
「妹がいる無菌室に行きたい」
「そっか...サファリパーク行ったことある?」
「どうしてお父さんと一緒にいるの?」
「どうして、、、」
「どうしてお父さんと一緒にいるの?」
「そうだよね、、、変だよね、、、、」
「お父さんは僕のこと嫌いだから帰って来ないの?」
下を向いたオバサンが長く黙って、ポロポロと大きな涙を流し、下を向いたまま言う。
「私も寂しくて、ごめんね、ずるいよね、、、お姉ちゃんと私の家に来れば、私毎日ご飯作るよ?」
「行かない、、」
「少しでも怖いことや、寂しい事があれば私に言って、なんでもいいから、、、、」
下を向いたまま涙を喉に詰まれせ震えた声を溢すように話すオバサンが、顔をあげて僕を見つめた。細い眉毛がクシャッと折れて、真っ赤な目が濡れていて、氷のように危うい光を反射した。震えた唇を動かしておばさんが続けて言った。
「私たちが助けてあげるから」
助けが必要なのはオバサンに見えた。僕は言った。
「わかった。」
「ごめんね、ごめんねユユ君、私が泣くのはずるいよね。」
「そうやって直してるんでしょ?」
「直してる?」
「僕わかるんだ、大人は泣いたり怒ったりして自分を直すんだって。」
「ごめんね弱い大人ばっかりで、ユユ君は優しいから、強い大人になれるよ。」
「ねぇなんで、なんでオバサンは大人なのにかわいいの?」
「ありがと、私は愛してる人がいるからね。女の人はみんな愛があれば可愛くなれるの」
オバサンはそう言って、下を向いたまま涙を拭い、僕に顔を向けると大袈裟に笑顔を作った。その笑顔は今までよりもずっと暖かかった
まだ太陽が元気なうちに、富士急ハイランドを出た。車内で隣に座っていた男の子が、ゲーム機を取り出して僕に言っう。
「俺、赤いギャラドス持ってるよ、見る?」
そう言われて僕は、言葉につまりながら言った。
「いや、僕ポケモンのゲームやった事ないから、」
「じゃあカセット貸してあげるよ。」
僕は嘘をついた
「ゲームあんまり好きじゃないんだ」
それを聞いたお父さんが急言う
「今日、ゲーム機買ってやろうか?」
ゲーム機がずっと欲しかった、友達と集まって僕以外皆ゲームをしている時間は惨めだった。でもお母さんにゲームが欲しいなんて言ったら困らせてしまうから言えなかった、しかし今なら欲しいと言えば買ってもらえる。僕は長く考えて言った。
「...いいよ」
お姉ちゃんとお母さんに僕だけ遊園地に連れて行ってもらったと言えないと思ったから。断られたお父さんは、次の言葉に困っていた、そんな僕達を見てオバサンが話を変える
「夕ご飯何を食べる?」
男の子が大きな声で言った
「すしー」
お父さんが僕に聞く
「寿司でいいか?」
「僕、生物食べれないよ」
お父さんが、無理に作った笑顔で言った
「そうだっけ?」
すし以外で何を食べようか話していると、男の子が、オバサンが乗る助手席のシートを蹴りながら
「すーしーがーいーい、すーしーがーいーいー」
そう言いながら大きな口で泣いていた、大人の前で、涙を拭いもしないで、泣き止もうともせずに、泣きたいだけ自由うに泣いていた。
「すしにするか、寿司屋って言ったって生物以外もあるしな」
地元で美味しいと評判の回らない寿司屋に入った。僕の隣にお父さんが座ったことが嬉しかった。子供として認められたような気がして、俺しかった。お酌をしようと、とっくりを手に取った。これが熱いと知らなくて、驚いてトックリをひっくり返してしまった、酒がお父さんにかかり、床に落ちたとっくりが割れて、オバサンがイヤーーっと悲鳴をあげて、お店のお客さんが皆同時にこっちを見る、お父さんが持っていた箸を僕に投げて叫んだ
「何やってるだぁこらぁあ」
そんなお父さんの声を聞いて男の子が大きな声で泣き出した。オバサンが男の子をすぐに抱きしめて、丁寧に頭を撫でてやりながら小さな声で
「大丈夫」
そう言い聞かせてあげていた。僕の隣にいるお父さんは黙って立ち上がり、お会計を済ませて店を出て行った。僕はこの光景を見ながらギュッと精一杯の力で口を閉じた、少しでも力を緩めれば我慢していた物が全部出そうだったから。
店の入り口の曇りガラスの奥にタバコを吸っているお父さんの姿がぼんやりと写っていた。遠い場所に行ってしまった憧れの背中が信号機に照らされて、赤く縁取られて揺れていた。
月を閉じ込めて、光だけを反射させる重たいベンツのドワを締めて、青いペンキが所々剥がれた団地のドアを開ける。玄関の電球はずっと前に切れて新しくなっていない。いつもの真っ暗な廊下を抜けて、リビイングに入ると、
「遅くなーーい?」
姉ちゃんの大きな声が響く。お姉ちゃんは、じょうろから飛び出た水のように透き通ったストレートの黒髪を、いつもポニーテールに纏めていて、眉毛と目尻は下がっていて、チビなのに態度がデカくて、3つ上なのに掃除、洗濯、料理を僕にやらせる、家で唯一の話し相手だ。
僕はいつもの姉ちゃんの姿を見て、やっと地球に帰ってこれた気がした。外から持ってきた空気を全部吐き出すと、
「あーーーー」
と声が漏れ、そして肺一杯にこの世界の空気を取り込んだ。お姉ちゃん‘が不思議そうな顔で僕を見ながら言う
「どうしたの?」
「これ。」
「え?何これ寿司じゃん!なんで寿司を食べられないあんたが寿司持ってるの?」
「お父さんと食べに行った」
お姉ちゃんが僕をじっくり観察して僕の喉元を触って言った。
「あんたこれどうしたの」
僕は自分の喉元を触ると傷ができていて血が出ていた、
「お父さんの箸があたった。」
お姉ちゃんが息を呑み込むのがはっきりと分かった。顔を下げたお姉ちゃんが僕の手を掴んで、もう一度顔を上げると涙を溜めて怖い顔をしていた。そして僕に言い聞かせるように言った。
「いい?次お父さんに会ったら逃げるんだよ」
「うん」
僕がそう言うと、お姉ちゃんが凄い勢いで寿司を食べ始めた。お姉ちゃんは僕が帰って来るのを、待っていて食事をとっていなかったんだ。僕がお姉ちゃんのために味噌汁を温めていると、
「ただいまぁ」
という声とともにお母さんが帰って来た。お母さんは、丸く大きな瞳に、筋が通った鼻で細い顎、絡まった白髪混じりの髪を帽子に押し込んで、いつも同じジャケットに、裾のほつれたジーンズ、化粧も最近しなくなった、写真で見た若い頃のお母さんはキレイだったのに、今のお母さんは砂場に落ちているリカちゃん人形みたいだった。
お姉ちゃんが急いで寿司をテーブルの下に隠す。お母さんはがリビングに入って、僕達に目線を向けることなく冷蔵庫の元へ真っすぐに歩いて、ビールを取り出しベランダに出てタバコに火を付けた。きっとお姉ちゃんが寿司を食べていた事にも気がついていないと思う。妹の骨髄移植のドナーが見つからないらしくて、最近僕達の顔をあまり見ない。今も背中を向けてタバコを吸っている。そんなお母さんに僕は言が言う。
「ねぇ、僕さっき帰って来たんだよ」
「そう?楽しかった?」
お母さんは背中を向けたまま言った。明るい声でそう話すお母さんがなんだか不気味だった。
「楽しかったって?、、、怒んないの?」
「怒られたいの?」
「友達はみんな6時に帰んないと親に怒られるんだよ、僕21時に帰って来たんだよ」
「どうしたの?」
自分がどうしたのかなんてわからない、でも一緒に遊んでいる友達が、門限を過ぎて帰ったら怒ってくれる大人がいることが羨ましかった。6時を過ぎると公園から子供はいなくなって、僕は一人になって、ボールを蹴っても返ってはこなかった。でもそんな寂しさは大した問題ではなかった。お父さんが帰ってきたら全部解決するから。お父さんが僕達のために働きに出ていて、僕達は幸せになる為の貯金をしていて、この貯金が溜まったらパンパンに溜まった幸せが僕達を包むんだ。そう思うと暗い公園で一人で遊んでいても楽しめた。でも今そごく不気味で怖いんだ、お母さんが、僕達の顔をあまり見ないのも、妹の話を大人があまりしないのも、お父さんが知らない子供にパパって呼ばれているのも、怖いんだ。昨日まではこの世界は、優しくて、僕の幸せを願っている友達だった。でも急に誰かが僕の世界に色塗りを始めたみたいに知らない物に変わっていっている。僕は世界の変化を止めて欲しくてお母さんに聞いた。
「お母さん僕達といて幸せ?」
僕がそう言うと家に帰ってきて初めてお母さんが僕の顔を見て、
「とっても幸せだよ。」
そう言った。急に痩せたせいでできた、目の下のシワを伸ばして笑顔を作りながら。だがお母さんの笑顔はすぐに固くなって、唇が震えてた。
「お風呂入ってくる」
お母さんはそう言って、足早に僕を通り過ぎて行った。また僕の顔を見ないで。少しするとお風呂場からあ母さんの鼻を啜る音が聞こえてきた。今日もお母さんはお風呂場で隠れて泣いている。いつも元気なお母さんが今どんな顔をしているのか昨日までは想像ができなかった。でも今はできる、富士急ハイランドでオバサンが泣いていた顔が頭から離れない、今お母さんはあのおばさんみたいに辛い顔をしているんだ。大人になるってそんなに悲しいの?僕よりも頭のいい大人はこの世界が辛い場所に見えるの?あの男の子は寿司が食べられないからって泣いているのを見て羨ましかった。そんな事で泣いていいの?君が泣いたら寿司が食べられた、でも、僕がどんなに泣いたって、お母さんの作り立てのご飯は食べられない。いつもサランラップに包まれた冷たいご飯をお姉ちゃんと二人でだけで食べるのは変わらない。でも今まではそれで満足だったんだ、なんの不満もなかった、僕はこの世界が大好きだったんだ。それなのに、、、、僕に教えないでよ。見ちゃったんだよ、あの男の子もお父さんの子供なのに、僕とあの子はなんでこんなに違うんんだよ。お母さんの髪はボロボロなのになんであのオバサンの髪はあんなにキレイなんだよ。知らない方が幸せだった、何も知らなければこの世界を嫌いになんてならなかった。僕の世界を返してよ。もしかして僕は大人に愛されていないの?あの男の子はベーム機を買ってもらえて、寿司が食べられないと泣いていた。あの男の子の機嫌に大人達が振り回されていた。でも僕の喜怒哀楽に付き合ってくれる大人なんて居ないじゃんか?すごく怖い、怖いから僕はお風呂のドア越しにお母さんに聞いた。
「ねぇ?誰のために泣いてるの?」
「何言ってるの?、、、、泣いてないわよ。」
「泣いてんじゃん、僕のために泣いてるの?」
「ごめんねユユ、、、いつもいつもあんたは、、、」
「ごめんねって言わないで」
自分でもビックリするほどの大きな声が出た。ごめんねって言わないで欲しいんだ、ごめんねって言われると僕が幸せじゃないって言われてるみたいだ、、、、僕にごめんねって言いながら泣く女の人を今日だけで二人見た。あのオバサンが言っていた言葉が頭から離れなくて僕はお母さんに言った。
「お母さんはなんでキレイじゃないの?」
「何言ってるの?」
「女の人は愛してる人がいるとキレイになるんじゃないの?」
「愛なんてのはね、靴みたいなものなの、女をキレイにしたり、遠くに連れて行ってくれたりするの、でもね、大きかったり小さかったりすると不恰好だし、痛いの。」
「じゃあお母さんの靴は小さいの?」
「ばかあだねぇ、私があんたの靴だよ。」
「でっかいよ」
僕は居間に戻りお姉ちゃんとテレビを見ていた。お風呂から出て髪を乾かしていたお母さんが、ドタドタと大きな足音を立てながら居間に走って飛び込み、
「さんまちゃんやってる、さんまちゃん」
そう言いながらテレビのチャンネルを魔法の杖のように振り回しって、恋のから騒ぎにテレビ画面を合わし、正座してブラウン管テレビを見つめる。お母さんはキラキラした目でテレビを見つめ、さんまさんがボケると、キャァアアと叫んで手を叩いて笑い、若返ったような、可愛らしさを取り戻したような、普段とは別人だった。さんまさんんがボケるまで笑うのを我慢しながら上目遣いでテレビを見つめ、口元を手で隠し、さんまさんがボケるとキァアアアと大きな声を出して笑い、恥ずかしそうに両方の手で顔を隠す。明石家さんまさんと、島田紳助さんがテレビに映る時間だけ、お母さんは、全てのストレスと、全ての問題を脱がされて能天気な女になる。の骨髄移植ドナーが見つからない、お父さんが帰ってこない、夜のパート代だけで僕達にご飯を食べさせている、僕が泣かしてしまった、そんなお母さんを、ブラウン管の向こうからこんなにも笑顔にできる明石家さんまさんがかっこ良かった。僕は隣に座るお姉ちゃんに言った。
「僕芸人になるよ。」
お姉ちゃんは目を丸くして僕に言った。
「あんた無口なのに?無理でしょ?」
続く。
「あの車ベンツだ」
「ベンツってなに?」
「金持ちの車だよ」
「どんぐらい金持ちの車?」
「すげ〜金持ちの車だよ!!どんな人が乗ってるのかな?見に行こうぜ。」
そうはしゃいでいた友達数人が“バタン“っとドアの閉まる音と同時に言葉を飲み込んだ。車から降りた大男がこっちに向かって歩いていた。運転手の男は40代前半で、薄い革ジャンにギンガムチェックのシャツ、ワンウォッシュデニムにチェルシーブーツ、そのコーディネイトの邪魔をするように大きなネックレスと指輪が金色に光っていた。細い目に吊り上がった眉毛、その顔は柔らかい場所なんて無くて、この場所に笑顔が作られるなんて想像できなかった。その運転手の顔を見て友達が言う。
「逃げる?」
僕が答えるのを待たずにみんな逃げようとしていた。そんな僕に運転手の男が低くてよく通る声で言った。
「ユユ」
友達が怯えた声で僕に言った。
「誰?」
「お父さん」
「ユユのお父さん、、、え?じゃあ車の中見せてもらえるのかな?」
「今度ね、先に学校行ってて」
友達たちは走り出し、ドタドタと道の先に消えてしまった。
僕はお父さんが帰ってくるのをずっと待っていた。僕の家は、母さんのパートのお金で母、姉、妹、僕の四人で生活していた。お金に余裕がなくて、借金取りの電話がうるさくて家の電話線はずっと抜いたままだった。お母さんはよく隠れて泣いていた。妹は病気で何年も帰って来ない。僕は毎日おねいちゃんと二人だけで食事をする。でもそんな事は全部へっちゃらだった。全部お父さんが帰って来れば可決するから。お母さんがいつも僕に言っていたんだ、
「お父さんは大工の仕事が忙しくて帰って来ないんだよ」
だからお父さんが帰って来る日は、いっぱい貯めたお金を持って帰ってきて、お母さんが働きに出なくなって、妹にいい薬を飲ましてあげて、家族がみんな揃って食事ができる日になるんだ。サザエさんを見るたびに憧れた、家族がみんな揃っている食事、あの憧れの食事が僕の家にも来るんだ。僕の知らない世界で家族のために一人で仕事をしているお父さん、あの白いピカピカの車いっぱいに幸せを乗せて迎えにきたんだ。
僕はお父さんの後をついていき、お父さんが車のドアを開けた、そこには男の子とキレイなオバサンが乗っていた。僕はこの町でスカートを履いているオバサンを始めて見た。白とピンクの花柄のスカートは薄い生地で服の上から少し太ももの形がわかった。黒くて細い髪は艶やかで、猫のように見開いた瞳に真横に伸びた眉毛が子供のようで、僕は、キレイなまま歳を取った女の人を始めて見た。急な知らない人の登場で驚き、黙ったままの僕にお父さんが言う。
「富士急ハイランドに行くぞ」
「今日、学校だよ」
「学校には連絡するから大丈夫だ、 休みの日は混んでるから今日行くんだよ。」
「お母さんは知ってるの?」
「知ってる。いいから行くぞ」
お父さんの声が少し大きくなり、僕が怖がるよりも前にキレイなオバサンが助手席から身を乗り出して
「富士急ハイランド行くぞーー」
そう言って手のひらを前に出して、僕とハイタッチをすると、
「かわいいー」
そう言って笑った。
男の子は僕よりも1歳か2歳年下で、車に乗った僕の方を見ることもなく、ぶつぶつと何かを話しながらゲームボーイアドバンスをプレイしていた。僕が黙っているとバックミラー越しにお父さんと目があって、すぐに恥ずかしくてなって僕が目を逸らすと、お父さんが僕に言った。
「お前もゲーム欲しいか?買ってやりゃー二人でできるもんな。」
「いらない」
僕はすぐに答えた、僕だけ遊園地に来て、ゲームまで買ってもらったら、妹と姉ちゃんに申し訳がないから。僕の答えを聞いて、お父さんが少し暗い顔になった。
盛り上がっていないのにしりとりをずっと続けながら僕たちは富士急ハイランドに着いた。お化け屋敷をリニューアルしたばかりの園内は、平日なのに人でごった返していた。
入り口のゲートを走って潜ろうとする男の子にキレイなオバサンが大きな声で言う。
「迷子になるから手を繋いでぇーー」
男の子はお土産屋さんの方を指さし、僕のお父さんの手を掴んで言った。
「パパー僕あれ欲しい」
僕は心の中で呟いた。そっか、お父さんはここに居たんだ、、、僕の知らない世界ってここだったんだ。お姉ちゃんがブランコから落ちて顔を怪我した日も、妹が入院した日も、骨折したお母さんに変わって、僕とお姉ちゃんが新聞配達をしていた日も、お父さんはここに居たんだ。何も言わない僕の姿を、お父さんが男の子に腕を引かれながら見た。僕は必死に表情を変えないように努力していた。自分が努力していたから分かった、お父さんも、オバサンも、同じ努力をしていた。このときの僕は、怒りや、悲しみなんて感じている余裕はなかった。きっとこの男の子よりもかわいい子供になれば、お父さんは帰ってくる、そう思ったから。お姉ちゃんに、妹に、お母さん、みんなまだお父さんが必要なんだ、僕は頑張って、連れてきてもらった遊園地を楽しんでいるように見せようとした。でも僕は、お父さんに話しかける事もできずに、ただお父さんの顔を見てお父さんが何を考えているのか探っているだけだった。本当は探っているのではなく、まだ僕のことを嫌いになってはいないか、答え合わせをしていた。そんな僕とは違って、男の子は
「パパ次はあれに乗ろうよ。パパ、○○君はこの前あのジェットコースーターに一人で乗ったんだよ。ねぇパパ見てぇ」
楽しそうで、かわいい子供だった。僕は心の中で呟いた、やっぱりあんなかわいい子供がいる家には帰りたくなるんだろうな、そう自分で呟いたのに、なんだか他人に言われているように感じて、急に悲しくなってきた。男の子にこの暗い顔を見られたくなくて僕は一番後ろを歩いていた、男の子と、お父さんがジェットコースターを乗りに行こうと僕を誘ったが、僕は怖いからとオバサンとベンチで待っている事にした。
オバサンが僕にチェロスを買ってくれた。人生で初めて食べるチェロスは、よくお母さんが作ってくれる、パンの耳を油で揚げたお菓子のような味がした。同じような味だが僕はお母さんが油で揚げたパンの耳の方が好きだった。黙ってチェロスを食べる僕にオバサンが優しい声で言った。
「ユユ君は遊園地あんまり好きじゃ無かったかな?」
「一人だから」
「そっかぁ、じゃぁ私とあの子といっぱい会って、少しずつ友達になったら楽しくなるかな?」
「わかんない」
「じゃあ次はユユ君のいきたいところに行こうね。どこに行きたい?」
「妹がいる無菌室に行きたい」
「そっか...サファリパーク行ったことある?」
「どうしてお父さんと一緒にいるの?」
「どうして、、、」
「どうしてお父さんと一緒にいるの?」
「そうだよね、、、変だよね、、、、」
「お父さんは僕のこと嫌いだから帰って来ないの?」
下を向いたオバサンが長く黙って、ポロポロと大きな涙を流し、下を向いたまま言う。
「私も寂しくて、ごめんね、ずるいよね、、、お姉ちゃんと私の家に来れば、私毎日ご飯作るよ?」
「行かない、、」
「少しでも怖いことや、寂しい事があれば私に言って、なんでもいいから、、、、」
下を向いたまま涙を喉に詰まれせ震えた声を溢すように話すオバサンが、顔をあげて僕を見つめた。細い眉毛がクシャッと折れて、真っ赤な目が濡れていて、氷のように危うい光を反射した。震えた唇を動かしておばさんが続けて言った。
「私たちが助けてあげるから」
助けが必要なのはオバサンに見えた。僕は言った。
「わかった。」
「ごめんね、ごめんねユユ君、私が泣くのはずるいよね。」
「そうやって直してるんでしょ?」
「直してる?」
「僕わかるんだ、大人は泣いたり怒ったりして自分を直すんだって。」
「ごめんね弱い大人ばっかりで、ユユ君は優しいから、強い大人になれるよ。」
「ねぇなんで、なんでオバサンは大人なのにかわいいの?」
「ありがと、私は愛してる人がいるからね。女の人はみんな愛があれば可愛くなれるの」
オバサンはそう言って、下を向いたまま涙を拭い、僕に顔を向けると大袈裟に笑顔を作った。その笑顔は今までよりもずっと暖かかった
まだ太陽が元気なうちに、富士急ハイランドを出た。車内で隣に座っていた男の子が、ゲーム機を取り出して僕に言っう。
「俺、赤いギャラドス持ってるよ、見る?」
そう言われて僕は、言葉につまりながら言った。
「いや、僕ポケモンのゲームやった事ないから、」
「じゃあカセット貸してあげるよ。」
僕は嘘をついた
「ゲームあんまり好きじゃないんだ」
それを聞いたお父さんが急言う
「今日、ゲーム機買ってやろうか?」
ゲーム機がずっと欲しかった、友達と集まって僕以外皆ゲームをしている時間は惨めだった。でもお母さんにゲームが欲しいなんて言ったら困らせてしまうから言えなかった、しかし今なら欲しいと言えば買ってもらえる。僕は長く考えて言った。
「...いいよ」
お姉ちゃんとお母さんに僕だけ遊園地に連れて行ってもらったと言えないと思ったから。断られたお父さんは、次の言葉に困っていた、そんな僕達を見てオバサンが話を変える
「夕ご飯何を食べる?」
男の子が大きな声で言った
「すしー」
お父さんが僕に聞く
「寿司でいいか?」
「僕、生物食べれないよ」
お父さんが、無理に作った笑顔で言った
「そうだっけ?」
すし以外で何を食べようか話していると、男の子が、オバサンが乗る助手席のシートを蹴りながら
「すーしーがーいーい、すーしーがーいーいー」
そう言いながら大きな口で泣いていた、大人の前で、涙を拭いもしないで、泣き止もうともせずに、泣きたいだけ自由うに泣いていた。
「すしにするか、寿司屋って言ったって生物以外もあるしな」
地元で美味しいと評判の回らない寿司屋に入った。僕の隣にお父さんが座ったことが嬉しかった。子供として認められたような気がして、俺しかった。お酌をしようと、とっくりを手に取った。これが熱いと知らなくて、驚いてトックリをひっくり返してしまった、酒がお父さんにかかり、床に落ちたとっくりが割れて、オバサンがイヤーーっと悲鳴をあげて、お店のお客さんが皆同時にこっちを見る、お父さんが持っていた箸を僕に投げて叫んだ
「何やってるだぁこらぁあ」
そんなお父さんの声を聞いて男の子が大きな声で泣き出した。オバサンが男の子をすぐに抱きしめて、丁寧に頭を撫でてやりながら小さな声で
「大丈夫」
そう言い聞かせてあげていた。僕の隣にいるお父さんは黙って立ち上がり、お会計を済ませて店を出て行った。僕はこの光景を見ながらギュッと精一杯の力で口を閉じた、少しでも力を緩めれば我慢していた物が全部出そうだったから。
店の入り口の曇りガラスの奥にタバコを吸っているお父さんの姿がぼんやりと写っていた。遠い場所に行ってしまった憧れの背中が信号機に照らされて、赤く縁取られて揺れていた。
月を閉じ込めて、光だけを反射させる重たいベンツのドワを締めて、青いペンキが所々剥がれた団地のドアを開ける。玄関の電球はずっと前に切れて新しくなっていない。いつもの真っ暗な廊下を抜けて、リビイングに入ると、
「遅くなーーい?」
姉ちゃんの大きな声が響く。お姉ちゃんは、じょうろから飛び出た水のように透き通ったストレートの黒髪を、いつもポニーテールに纏めていて、眉毛と目尻は下がっていて、チビなのに態度がデカくて、3つ上なのに掃除、洗濯、料理を僕にやらせる、家で唯一の話し相手だ。
僕はいつもの姉ちゃんの姿を見て、やっと地球に帰ってこれた気がした。外から持ってきた空気を全部吐き出すと、
「あーーーー」
と声が漏れ、そして肺一杯にこの世界の空気を取り込んだ。お姉ちゃん‘が不思議そうな顔で僕を見ながら言う
「どうしたの?」
「これ。」
「え?何これ寿司じゃん!なんで寿司を食べられないあんたが寿司持ってるの?」
「お父さんと食べに行った」
お姉ちゃんが僕をじっくり観察して僕の喉元を触って言った。
「あんたこれどうしたの」
僕は自分の喉元を触ると傷ができていて血が出ていた、
「お父さんの箸があたった。」
お姉ちゃんが息を呑み込むのがはっきりと分かった。顔を下げたお姉ちゃんが僕の手を掴んで、もう一度顔を上げると涙を溜めて怖い顔をしていた。そして僕に言い聞かせるように言った。
「いい?次お父さんに会ったら逃げるんだよ」
「うん」
僕がそう言うと、お姉ちゃんが凄い勢いで寿司を食べ始めた。お姉ちゃんは僕が帰って来るのを、待っていて食事をとっていなかったんだ。僕がお姉ちゃんのために味噌汁を温めていると、
「ただいまぁ」
という声とともにお母さんが帰って来た。お母さんは、丸く大きな瞳に、筋が通った鼻で細い顎、絡まった白髪混じりの髪を帽子に押し込んで、いつも同じジャケットに、裾のほつれたジーンズ、化粧も最近しなくなった、写真で見た若い頃のお母さんはキレイだったのに、今のお母さんは砂場に落ちているリカちゃん人形みたいだった。
お姉ちゃんが急いで寿司をテーブルの下に隠す。お母さんはがリビングに入って、僕達に目線を向けることなく冷蔵庫の元へ真っすぐに歩いて、ビールを取り出しベランダに出てタバコに火を付けた。きっとお姉ちゃんが寿司を食べていた事にも気がついていないと思う。妹の骨髄移植のドナーが見つからないらしくて、最近僕達の顔をあまり見ない。今も背中を向けてタバコを吸っている。そんなお母さんに僕は言が言う。
「ねぇ、僕さっき帰って来たんだよ」
「そう?楽しかった?」
お母さんは背中を向けたまま言った。明るい声でそう話すお母さんがなんだか不気味だった。
「楽しかったって?、、、怒んないの?」
「怒られたいの?」
「友達はみんな6時に帰んないと親に怒られるんだよ、僕21時に帰って来たんだよ」
「どうしたの?」
自分がどうしたのかなんてわからない、でも一緒に遊んでいる友達が、門限を過ぎて帰ったら怒ってくれる大人がいることが羨ましかった。6時を過ぎると公園から子供はいなくなって、僕は一人になって、ボールを蹴っても返ってはこなかった。でもそんな寂しさは大した問題ではなかった。お父さんが帰ってきたら全部解決するから。お父さんが僕達のために働きに出ていて、僕達は幸せになる為の貯金をしていて、この貯金が溜まったらパンパンに溜まった幸せが僕達を包むんだ。そう思うと暗い公園で一人で遊んでいても楽しめた。でも今そごく不気味で怖いんだ、お母さんが、僕達の顔をあまり見ないのも、妹の話を大人があまりしないのも、お父さんが知らない子供にパパって呼ばれているのも、怖いんだ。昨日まではこの世界は、優しくて、僕の幸せを願っている友達だった。でも急に誰かが僕の世界に色塗りを始めたみたいに知らない物に変わっていっている。僕は世界の変化を止めて欲しくてお母さんに聞いた。
「お母さん僕達といて幸せ?」
僕がそう言うと家に帰ってきて初めてお母さんが僕の顔を見て、
「とっても幸せだよ。」
そう言った。急に痩せたせいでできた、目の下のシワを伸ばして笑顔を作りながら。だがお母さんの笑顔はすぐに固くなって、唇が震えてた。
「お風呂入ってくる」
お母さんはそう言って、足早に僕を通り過ぎて行った。また僕の顔を見ないで。少しするとお風呂場からあ母さんの鼻を啜る音が聞こえてきた。今日もお母さんはお風呂場で隠れて泣いている。いつも元気なお母さんが今どんな顔をしているのか昨日までは想像ができなかった。でも今はできる、富士急ハイランドでオバサンが泣いていた顔が頭から離れない、今お母さんはあのおばさんみたいに辛い顔をしているんだ。大人になるってそんなに悲しいの?僕よりも頭のいい大人はこの世界が辛い場所に見えるの?あの男の子は寿司が食べられないからって泣いているのを見て羨ましかった。そんな事で泣いていいの?君が泣いたら寿司が食べられた、でも、僕がどんなに泣いたって、お母さんの作り立てのご飯は食べられない。いつもサランラップに包まれた冷たいご飯をお姉ちゃんと二人でだけで食べるのは変わらない。でも今まではそれで満足だったんだ、なんの不満もなかった、僕はこの世界が大好きだったんだ。それなのに、、、、僕に教えないでよ。見ちゃったんだよ、あの男の子もお父さんの子供なのに、僕とあの子はなんでこんなに違うんんだよ。お母さんの髪はボロボロなのになんであのオバサンの髪はあんなにキレイなんだよ。知らない方が幸せだった、何も知らなければこの世界を嫌いになんてならなかった。僕の世界を返してよ。もしかして僕は大人に愛されていないの?あの男の子はベーム機を買ってもらえて、寿司が食べられないと泣いていた。あの男の子の機嫌に大人達が振り回されていた。でも僕の喜怒哀楽に付き合ってくれる大人なんて居ないじゃんか?すごく怖い、怖いから僕はお風呂のドア越しにお母さんに聞いた。
「ねぇ?誰のために泣いてるの?」
「何言ってるの?、、、、泣いてないわよ。」
「泣いてんじゃん、僕のために泣いてるの?」
「ごめんねユユ、、、いつもいつもあんたは、、、」
「ごめんねって言わないで」
自分でもビックリするほどの大きな声が出た。ごめんねって言わないで欲しいんだ、ごめんねって言われると僕が幸せじゃないって言われてるみたいだ、、、、僕にごめんねって言いながら泣く女の人を今日だけで二人見た。あのオバサンが言っていた言葉が頭から離れなくて僕はお母さんに言った。
「お母さんはなんでキレイじゃないの?」
「何言ってるの?」
「女の人は愛してる人がいるとキレイになるんじゃないの?」
「愛なんてのはね、靴みたいなものなの、女をキレイにしたり、遠くに連れて行ってくれたりするの、でもね、大きかったり小さかったりすると不恰好だし、痛いの。」
「じゃあお母さんの靴は小さいの?」
「ばかあだねぇ、私があんたの靴だよ。」
「でっかいよ」
僕は居間に戻りお姉ちゃんとテレビを見ていた。お風呂から出て髪を乾かしていたお母さんが、ドタドタと大きな足音を立てながら居間に走って飛び込み、
「さんまちゃんやってる、さんまちゃん」
そう言いながらテレビのチャンネルを魔法の杖のように振り回しって、恋のから騒ぎにテレビ画面を合わし、正座してブラウン管テレビを見つめる。お母さんはキラキラした目でテレビを見つめ、さんまさんがボケると、キャァアアと叫んで手を叩いて笑い、若返ったような、可愛らしさを取り戻したような、普段とは別人だった。さんまさんんがボケるまで笑うのを我慢しながら上目遣いでテレビを見つめ、口元を手で隠し、さんまさんがボケるとキァアアアと大きな声を出して笑い、恥ずかしそうに両方の手で顔を隠す。明石家さんまさんと、島田紳助さんがテレビに映る時間だけ、お母さんは、全てのストレスと、全ての問題を脱がされて能天気な女になる。の骨髄移植ドナーが見つからない、お父さんが帰ってこない、夜のパート代だけで僕達にご飯を食べさせている、僕が泣かしてしまった、そんなお母さんを、ブラウン管の向こうからこんなにも笑顔にできる明石家さんまさんがかっこ良かった。僕は隣に座るお姉ちゃんに言った。
「僕芸人になるよ。」
お姉ちゃんは目を丸くして僕に言った。
「あんた無口なのに?無理でしょ?」
続く。
最新写メ日記
月別アーカイブ
全在籍セラピスト最新写メ日記
秘密基地グループ
-
東京エリア
東京秘密基地本店 渋谷秘密基地 新宿秘密基地 池袋秘密基地 立川秘密基地 上野秘密基地 品川秘密基地 錦糸町秘密基地 八王子秘密基地 町田秘密基地 六本木秘密基地 銀座秘密基地 青山秘密基地 世田谷秘密基地 赤坂秘密基地 吉祥寺秘密基地 恵比寿秘密基地 赤羽秘密基地 西麻布秘密基地 新大久保秘密基地 中野秘密基地 -
関東エリア
横浜秘密基地 千葉秘密基地 さいたま秘密基地 宇都宮秘密基地 川崎秘密基地 群馬秘密基地 西川口秘密基地 湘南秘密基地 茨城秘密基地 船橋秘密基地 大宮秘密基地 柏秘密基地 松戸秘密基地 水戸秘密基地 舞浜秘密基地 越谷秘密基地準備中 -
北海道・東北エリア
札幌秘密基地 仙台秘密基地 郡山秘密基地 山形秘密基地 岩手秘密基地 青森秘密基地募集中 秋田秘密基地募集中 -
北陸・甲信越エリア
新潟秘密基地 長野秘密基地 甲府秘密基地 金沢秘密基地募集中 富山秘密基地募集中 福井秘密基地募集中 -
東海エリア
静岡秘密基地 名古屋秘密基地 三重秘密基地 岐阜秘密基地 浜松秘密基地 岡崎秘密基地 豊橋秘密基地 藤が丘秘密基地 -
関西エリア
大阪秘密基地 神戸秘密基地 なんば秘密基地 京都秘密基地 梅田秘密基地 堺東秘密基地 京橋秘密基地 滋賀秘密基地募集中 奈良秘密基地募集中 和歌山秘密基地募集中 -
中国エリア
広島秘密基地 岡山秘密基地 山口秘密基地 出雲秘密基地募集中 鳥取秘密基地募集中 -
四国エリア
香川秘密基地 徳島秘密基地 高知秘密基地募集中 松山秘密基地募集中 -
九州・沖縄エリア
博多秘密基地 沖縄秘密基地 鹿児島秘密基地 大分秘密基地 北九州秘密基地 宮崎秘密基地 佐賀秘密基地 熊本秘密基地 長崎秘密基地 中洲秘密基地 久留米秘密基地募集中