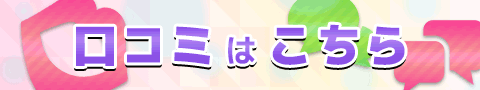5/4 17:14 UP! 笑顔が似合わない人間なんていない YUYU(ユユ)(29)

僕は瞬(坂本 瞬 サカモト シュン )に会うために車を走らせていた。
瞬との出会いは1年ほど前だった。 家の近くで、深夜でも街灯が灯っている量販店の駐車場で僕は一人でいつもスケボーをしていた。その駐車場は不良の溜まり場にもなっていて、いくつかのグループが点々と離れた場所で車やバイクを見せびらかすように並べて、人が束になってたむろしていた。いくつかのグループの一つが僕の先輩達が居るグループだったので、僕は怖い思いをしたことは無かった。その日も僕は一人でスケボーをしていた。
すると一人の男が僕の方に歩いてきた。その男はニッカポッカに和柄の鯉口シャツ、夜中なのにサングラスをかけ、高いタッパで下駄をガランガランと引きずって歩いていた。話ができる人間には見えなかった。僕はスケボーから降りて緊張で筋肉を膨らませていた。その下駄の男が僕の前に立って何かを言った、しかしその声は爆音のバイクにかき消されて聞こえなかった、一台のバイクがすごいスピードで僕と下駄の男の隣に急停車し、男が二人バイクから降りてきた。その二人は僕の先輩だった。先輩が大きな声を出して下駄の男に近づく。
「なんでぇ俺の後輩になんか文句でもあんだけぇ?」
下駄の男も先輩二人に近づいてドスの効いた声で言った。
「うるせーなオメーらに話すこんなんねぇーつこん」
その声は洞窟で重い何かを引きずるような声だった。二人いる先輩の片方が小さな声で言う
「こいつ瞬ずら」
もう一人の先輩がさらに下駄の男に近づくと先輩の被っていた帽子のツバが下駄の男のおでこにぶつかって、瞬の首の血管が浮き上がる。先輩が嫌な笑顔を見せて言う
「お前中心で〇〇くんをボコったみてーじゃん、お前今探させれてっぞ、こんな所にいていいだけ?」
バイクのアイドリング音が不規則に僕の鼓動を煽る。僕は急に現れた瞬という大男の目的が分からず緊張と興奮で震えていた。僕がこの喧嘩を止めないといけない、この先輩に喧嘩をさせてはいけない、この先輩は喧嘩が弱いからいつも警棒を持っている、警棒なんか振り回したら警察沙汰になる、僕は勇気を出して言った。
「俺と話してーずら?」
下駄の男が金のネックレスを触っ触りながら僕の方を見て笑って言う。
「二人で話しちゃ」
「そうしっか」
僕がそう言って下駄の男の後について行こうとすると先輩が
「俺も行くから」
そう言って一緒にこようとした、僕は先輩を説得して一人で下駄の男の車に乗った。フルスモークのハイエースは運転席と助手席以外の座席は外されており、後ろはガランと広く不気味だった。行き先を伝えられずに進む車内はT.Iのラップが爆音で流れていた。僕の日常に急にぶつかって来たこの男は何を考えているのだろうか?今日の落とし所が分からずに嫌な想像ばかりが広がる。今日は昨日と同じ布団で寝れるのだろうか?あんな不良の溜まり場のな駐車場でスケボーなんてしなければよかった、そう今更後悔していた。急に車が止まりエンジンを切られた車内は音を吸収してフルスモックの窓から見た外は深海のように暗かった。下駄の男が車外に出たので、僕も車を降りた、そこは小さな公園だった。下駄の男が煙草に火をつける。一瞬だけその大きなサングラスが光って、カーテンを閉めるようにまた姿が夜に消える。下駄の男が咳ばらいをして、僕に言った。
「スケボーってそんねん楽しーんけぇ?」
その声はさっきまでのドスの効いた声ではなく、明るくて少年のような透明な声だった。僕はなんの話が始まろうとしているのか分からずに聞いた。
「どーゆーこと?」
「俺ヤンキー辞めてーつこん」
僕はしっかり考えて、時間をかけて言った。
「どーゆーこと?」
「毎日さ仲間のみんながスケボーしてるお兄さんを見てバカにしてんだよ、毎日同じことしてんのに全然上手くなんねーなって、毎日一人でただずっとジャンプしてるだけで、賽の河原だって。」
僕はこの男が何の話をしているのかまだ理解できなっかった。しかし話ながらサングラスを外したこの男の表情がタバコの火種でぼんやりと見えた。その顔は真剣で怖い場所はどこにも無かった。男は上手に言葉は出なくて何度もつまずきながら、でもその熱量を高めながら話しを続けた。
「でもそんなに熱中できるってカコイイって俺思うんだ、、、俺最近仕事始めたんだ、、、俺部活もやった事無いし、高校も行って無いし、何かを本気でやった事無いんだ、、、だからケンカするんんだよ、熱くなるから、、、でも親父が大工の棟梁やってるんだけど、親父に最近大工の仕事に連れてかれたんだよ、、、でもさ、、、そしたらさ、仕事って楽しいんだよ、仕事仲間と全員で同じ目標に向かって汗を流してさ、はじめて熱中できる物ができたんだよ。仕事やり出したらさ、ケンカするの嫌になってきて、、、それにあいつら仕事もしないで小狡いことでお金稼いで、悪口と不満しか言わなくて、頑張ってる人のことを笑って、楽しくないだ一緒にいても。一緒に居たくないのに、、、俺仕事終わったら一人だし、やることないし、あいつらが迎えにくるから何となく一緒にいるんだけど、、、ケンカしたくないのに俺体デカいからさ、揉め事があったりするとケンカを頼まれるんだよ、、、もう嫌なんだよヤンキーの世界が、、、そんな事考えてたらお兄さんがスケボーしてるのが見えて、みんなに笑われてるのにお構いなしに楽しそーで、熱中してて、かっこいいーって思った」
僕はずっと我慢していたがついに我慢できなくなって、下駄の男に大声で言った。
「俺笑われてるって知らなかったんだけど」
「耐えぬいてたんじゃないの?」
「ちげぇーよ!!俺はみんなの憧れの的になりたくて、わざわざ夜中でも人の多いあの駐車場でスケボーを見せびらかしてたんだよ!」
「え?だせぇぇ」
「だせぇて何だよ!!さっきまでかっこいいって言ってたじゃん!」
「だせーよ!でも夜中でスケボーができる場所ってあそこしか無いでしょ?」
「いや、それがさぁ小瀬スポーツ公園のグラウンドに近い入り口があるじゃん?」
「だせーよ!!」
「まだださくねーだろ!!!そのグラウンドに近い方の入り口にスケボーできそうな場所があるんだけど、そこのトイレがお化け出るって聞いて、怖くて出来ないんだよ」
「...」
「なんか言えよ」
「あ~、UNO!!!」
「UNOやってねーよ!!!」
僕と下駄の男は息ができないほど笑って、お互いの肩を叩き合った。笑ってるお互いの顔を見合ってまた笑った。不思議だった、もうこの瞬間から僕達は親友だった、今日あったばかりのこの男と僕ははずっと一緒にいるんだろうなってなぜだかそう確信してた。そしてお互いの笑いが落ち着くのを待ってから、僕は聞いた。
「で何が言いたいの?」
「スケボー始めたら俺、ヤンキーとツルまなくてすむだろ、スケボーが誘いを断る理由になるし、それにスケボーなら一人でできるし、、、だからスケボーをさぁ、どれを買えばいいのか教えてくれよ!」
「二人でやればいいだろ!!」
「俺とやってくれるの?俺お前の先輩に嫌われてるよ?」
「俺もお前も、ヤンキーじゃないから関係ないよ!!」
「ありがと、、、」
「そんな顔するなよ」
この日から僕と瞬は毎日のように遊んだ。瞬はスケボーをしていても、お酒を飲んでいてもいつも同じ話をする。
「ユユも大工になれよ、一緒に修行してさ二人で独立して会社作ろうぜ!!俺たち二人なら最強だろ!!」
僕はいつも嫌そうな顔で同じ回答をする。
「やだよ」
でも今日は、この会話が瞬とできればいいと願っていた。
僕は車から降りて目的地の病室のドアを開けた。四畳半ほどの四角い空間に入ると、そこには瞬と瞬の彼女のマリー(吉岡 真莉 ヨシオカ マリ)がいた。
「ユユ来てくれたの?」
いつにも増して元気な声で僕に話しかける瞬。そんな瞬の下半身は二つのどでかいアームからでたワイヤーがガッチリと固定していた。そして腰の右から左へ太いボルトが貫通し、シーツを血が黒く染めていた。血の臭いなのか、薬の臭いなのか、じっとりとした嫌な匂いが部屋に充満していた。映画の野戦病院のような光景に吐き気と汗が止まらなかった。僕の呼吸が短くそして浅くなる。事故の前の日も僕と瞬は一緒にスケボーをしていたのに。あの日、機械のように精密でそしてアグレッシブに動いていた太い足は、木の根のような色をしていた。十日前、大工の仕事で座って作業をしていた瞬の上にクレーンで吊り上げた通し柱が滑り落ちた。事故の瞬間、瞬の腰袋に入っていたトンカチの鋼が真っ二つになったそうだ。今瞬の腰はどうなっているのか僕には想像ができなかった。鋼でできたトンカチが耐えられない衝撃が僕の友達を襲ったんだ。血で汚れたシーツを見ると僕の心臓は体に血を送るのをやめて、手足が痺れた。こんなに酷いことになっているなんて僕は知らなかった。柱の下敷きになったって聞いた時は、ちょっとした骨折ぐらいだと思っていた。それなのに現実は...この匂いと、血の色に僕は怯えていて、ショックで立っているのがやっとだった。それなのに瞬はいつもと変わらずに明るく話す。
「手術受けてずっと面会できなくて、でやっと昨日面会できるようになったんだけどさ、マリーが昨日面会に来てくれて、でビックリしたよ!マリーこのタイミングでタトゥー入れてたからね!!俺がさーずっとタトゥー入れないでって反対してたの、で、俺が入院して今しかないって急いで入れに行ったんだよ!絶対に今じゃなくない?」
「違うから!瞬が入院したから私が強く生きなきゃと思って強くなる決意として入れたの!」
「強くなるって、マリーがなんのタトゥー入れたと思う?、、、ポッチャマだからね!!!ポケモンのポッチャマ!ポッチャマ弱いだろ!!強く生きたいのなら、エンペルトでよくない?」
「エンペルト可愛くないもん!!」
マリーがそう言って大きな口で笑い、そんなマリーの顔を覗きこんで瞬が笑い、二人で顔を見合わせてまた大きく笑った。そしてもっと大きな声で瞬が僕に言った。
「俺のためにとか言ってるけど、絶対にタトゥー入れたいだけだよね!どう思うユユ?」
「ちょっと飲み物買いに行ってくるよ」
僕はそう言ってこの病室から出ようとした。僕にはこれ以上元気な瞬の姿を見る勇気が無かった。
「私、売店の場所教えるよ」
マリーがそう言って僕と二人で病室を出た。病室を出るとマリーの顔から力がなくなって、歩いてる速度が段々と遅くなって立ち止まり、壁にもだれて独り言ののように話し出した。
「あのクレーンの運転手殺してやる、そう言ったらね、かわいそうだろって言うんだよ。あいつ本当に頭おかしいよね、、、、、、瞬ね、もう歩けないんだって」
そう言うと、マリーが泣き出した。震える小さな手で顔をおおいながら。泣きじゃくるマリーの肩を支えて
「大丈夫だよ、大丈夫だよ、、、瞬には俺もマリーもついてるんだからさ、、、」
僕はマリーに何かしてあげたいけど、何をしていいのか分からずに、ただソワソワしていた。そんな僕にマリーが。
「ユユは瞬の所にいてあげて、私は涙が出なくなったら戻るから。」
僕は一人で病室に戻った。
「ユユそのでかい袋何入ってんの?」
「プレゼント」
そう言ってずっと背中に背負っていた袋を僕は瞬に渡した。瞬が袋を開いて笑顔になって顔を上げて言う。
「ガールのスケボーじゃん。マジでくれるの?...でもこれ、、、マリーにあげていい?あいつも始めたがってたから...今度さ、マリーをスケボーに連れて行ってあげて」
瞬が無垢な笑顔でそう言った。なんて残酷なプレゼントを渡してしまったんだ。今度っていつだ?自分がバカすぎて情けなかった。瞬が、優しくて、明るくて、涙を我慢できなかった。どんなに強く我慢しても、涙を止められなかった。こんなに優しい瞬がどうして。悔しくて悔しくて、何が悔しいのかも解らなかった。そんな僕の顔を見て瞬が言った。
「ごめんね、ユユ」
「いや...」
何でお前が謝るんだよ、そう言ったいのに声が出なかった。瞬はゆっくりと穏やかに話し出した
「全部なくなったな、、、全部だ、仕事も、ユユも、マリーも全部だ」
「俺とマリーはまだいるだろ」
自分でもびっくりするほど大きな声が出た。でも瞬は驚きもしないで続けた
「いいんだよ、俺は悪い奴なんだよ、いろんな人を殴ってきた。ユユお前は俺のことを友達だって言ってくれるけど、実際は違ったよ、対等なんかじゃなかった、ユユは与える人間で、俺は奪う人間だ。お前とマリーは俺の憧れなんだよ、、、」
「関係ねーよ友達だろ、欲しいもんなら全部やるよ、奪ってけよ、、、」
僕の言葉を聞いた瞬が大きな声で叫んだ、くしゃくしゃの顔で、大粒の涙を流しながら。
「お前達から何も奪いたくないんだよ俺んなかと一緒にいたら、、、」
痛くて長い沈黙が続いた。すると、看護師が入ってきて、
「外で待っていてください」
そう言って、僕は病室を出された。病室の中の会話が廊下まで聞こえた。
「ア゛ア゛ァーー」
「少しだけ我慢してください」
「ア゛ア゛ァーー」
まるで洞窟の中で大きな獣が叫ぶような声が音のない廊下に響いて、鳥肌だらけの私の全身をチクチク刺した。下を見るとスニーカーに汚れがついていた。瞬ははもう履くことも出来ないスニーカーに。
この日僕は強く誓った。どんな瞬間も与える側の人間であろうと。奪われようが、騙されようが関係ない、底なしの情熱と笑顔で人に寄り添うんだよ、優しさをわけた人が遠慮しないように、卑屈にならないように、、、
過去や立場や状況は全て関係ない、この地球に不幸になっていい人間なんて一人もいない。笑顔が似合わない人間なんて一人もいない。だから、だから、僕と出会った人は全員まとめて笑顔にしたい。
そしてあの日から7年がたった今。他人への理解も、人を笑顔にするスキルも、エッチなスキルも深まった。是非ともご予約ください。何かに疲れたあなたの心も体も僕が温めて、笑顔にいたします。損はさせません。面白くて、優しくて、甘くて、ドキッとして、エッチで、心地いい痺れが襲うそんな時間を二人で過ごしませんか?
瞬との出会いは1年ほど前だった。 家の近くで、深夜でも街灯が灯っている量販店の駐車場で僕は一人でいつもスケボーをしていた。その駐車場は不良の溜まり場にもなっていて、いくつかのグループが点々と離れた場所で車やバイクを見せびらかすように並べて、人が束になってたむろしていた。いくつかのグループの一つが僕の先輩達が居るグループだったので、僕は怖い思いをしたことは無かった。その日も僕は一人でスケボーをしていた。
すると一人の男が僕の方に歩いてきた。その男はニッカポッカに和柄の鯉口シャツ、夜中なのにサングラスをかけ、高いタッパで下駄をガランガランと引きずって歩いていた。話ができる人間には見えなかった。僕はスケボーから降りて緊張で筋肉を膨らませていた。その下駄の男が僕の前に立って何かを言った、しかしその声は爆音のバイクにかき消されて聞こえなかった、一台のバイクがすごいスピードで僕と下駄の男の隣に急停車し、男が二人バイクから降りてきた。その二人は僕の先輩だった。先輩が大きな声を出して下駄の男に近づく。
「なんでぇ俺の後輩になんか文句でもあんだけぇ?」
下駄の男も先輩二人に近づいてドスの効いた声で言った。
「うるせーなオメーらに話すこんなんねぇーつこん」
その声は洞窟で重い何かを引きずるような声だった。二人いる先輩の片方が小さな声で言う
「こいつ瞬ずら」
もう一人の先輩がさらに下駄の男に近づくと先輩の被っていた帽子のツバが下駄の男のおでこにぶつかって、瞬の首の血管が浮き上がる。先輩が嫌な笑顔を見せて言う
「お前中心で〇〇くんをボコったみてーじゃん、お前今探させれてっぞ、こんな所にいていいだけ?」
バイクのアイドリング音が不規則に僕の鼓動を煽る。僕は急に現れた瞬という大男の目的が分からず緊張と興奮で震えていた。僕がこの喧嘩を止めないといけない、この先輩に喧嘩をさせてはいけない、この先輩は喧嘩が弱いからいつも警棒を持っている、警棒なんか振り回したら警察沙汰になる、僕は勇気を出して言った。
「俺と話してーずら?」
下駄の男が金のネックレスを触っ触りながら僕の方を見て笑って言う。
「二人で話しちゃ」
「そうしっか」
僕がそう言って下駄の男の後について行こうとすると先輩が
「俺も行くから」
そう言って一緒にこようとした、僕は先輩を説得して一人で下駄の男の車に乗った。フルスモークのハイエースは運転席と助手席以外の座席は外されており、後ろはガランと広く不気味だった。行き先を伝えられずに進む車内はT.Iのラップが爆音で流れていた。僕の日常に急にぶつかって来たこの男は何を考えているのだろうか?今日の落とし所が分からずに嫌な想像ばかりが広がる。今日は昨日と同じ布団で寝れるのだろうか?あんな不良の溜まり場のな駐車場でスケボーなんてしなければよかった、そう今更後悔していた。急に車が止まりエンジンを切られた車内は音を吸収してフルスモックの窓から見た外は深海のように暗かった。下駄の男が車外に出たので、僕も車を降りた、そこは小さな公園だった。下駄の男が煙草に火をつける。一瞬だけその大きなサングラスが光って、カーテンを閉めるようにまた姿が夜に消える。下駄の男が咳ばらいをして、僕に言った。
「スケボーってそんねん楽しーんけぇ?」
その声はさっきまでのドスの効いた声ではなく、明るくて少年のような透明な声だった。僕はなんの話が始まろうとしているのか分からずに聞いた。
「どーゆーこと?」
「俺ヤンキー辞めてーつこん」
僕はしっかり考えて、時間をかけて言った。
「どーゆーこと?」
「毎日さ仲間のみんながスケボーしてるお兄さんを見てバカにしてんだよ、毎日同じことしてんのに全然上手くなんねーなって、毎日一人でただずっとジャンプしてるだけで、賽の河原だって。」
僕はこの男が何の話をしているのかまだ理解できなっかった。しかし話ながらサングラスを外したこの男の表情がタバコの火種でぼんやりと見えた。その顔は真剣で怖い場所はどこにも無かった。男は上手に言葉は出なくて何度もつまずきながら、でもその熱量を高めながら話しを続けた。
「でもそんなに熱中できるってカコイイって俺思うんだ、、、俺最近仕事始めたんだ、、、俺部活もやった事無いし、高校も行って無いし、何かを本気でやった事無いんだ、、、だからケンカするんんだよ、熱くなるから、、、でも親父が大工の棟梁やってるんだけど、親父に最近大工の仕事に連れてかれたんだよ、、、でもさ、、、そしたらさ、仕事って楽しいんだよ、仕事仲間と全員で同じ目標に向かって汗を流してさ、はじめて熱中できる物ができたんだよ。仕事やり出したらさ、ケンカするの嫌になってきて、、、それにあいつら仕事もしないで小狡いことでお金稼いで、悪口と不満しか言わなくて、頑張ってる人のことを笑って、楽しくないだ一緒にいても。一緒に居たくないのに、、、俺仕事終わったら一人だし、やることないし、あいつらが迎えにくるから何となく一緒にいるんだけど、、、ケンカしたくないのに俺体デカいからさ、揉め事があったりするとケンカを頼まれるんだよ、、、もう嫌なんだよヤンキーの世界が、、、そんな事考えてたらお兄さんがスケボーしてるのが見えて、みんなに笑われてるのにお構いなしに楽しそーで、熱中してて、かっこいいーって思った」
僕はずっと我慢していたがついに我慢できなくなって、下駄の男に大声で言った。
「俺笑われてるって知らなかったんだけど」
「耐えぬいてたんじゃないの?」
「ちげぇーよ!!俺はみんなの憧れの的になりたくて、わざわざ夜中でも人の多いあの駐車場でスケボーを見せびらかしてたんだよ!」
「え?だせぇぇ」
「だせぇて何だよ!!さっきまでかっこいいって言ってたじゃん!」
「だせーよ!でも夜中でスケボーができる場所ってあそこしか無いでしょ?」
「いや、それがさぁ小瀬スポーツ公園のグラウンドに近い入り口があるじゃん?」
「だせーよ!!」
「まだださくねーだろ!!!そのグラウンドに近い方の入り口にスケボーできそうな場所があるんだけど、そこのトイレがお化け出るって聞いて、怖くて出来ないんだよ」
「...」
「なんか言えよ」
「あ~、UNO!!!」
「UNOやってねーよ!!!」
僕と下駄の男は息ができないほど笑って、お互いの肩を叩き合った。笑ってるお互いの顔を見合ってまた笑った。不思議だった、もうこの瞬間から僕達は親友だった、今日あったばかりのこの男と僕ははずっと一緒にいるんだろうなってなぜだかそう確信してた。そしてお互いの笑いが落ち着くのを待ってから、僕は聞いた。
「で何が言いたいの?」
「スケボー始めたら俺、ヤンキーとツルまなくてすむだろ、スケボーが誘いを断る理由になるし、それにスケボーなら一人でできるし、、、だからスケボーをさぁ、どれを買えばいいのか教えてくれよ!」
「二人でやればいいだろ!!」
「俺とやってくれるの?俺お前の先輩に嫌われてるよ?」
「俺もお前も、ヤンキーじゃないから関係ないよ!!」
「ありがと、、、」
「そんな顔するなよ」
この日から僕と瞬は毎日のように遊んだ。瞬はスケボーをしていても、お酒を飲んでいてもいつも同じ話をする。
「ユユも大工になれよ、一緒に修行してさ二人で独立して会社作ろうぜ!!俺たち二人なら最強だろ!!」
僕はいつも嫌そうな顔で同じ回答をする。
「やだよ」
でも今日は、この会話が瞬とできればいいと願っていた。
僕は車から降りて目的地の病室のドアを開けた。四畳半ほどの四角い空間に入ると、そこには瞬と瞬の彼女のマリー(吉岡 真莉 ヨシオカ マリ)がいた。
「ユユ来てくれたの?」
いつにも増して元気な声で僕に話しかける瞬。そんな瞬の下半身は二つのどでかいアームからでたワイヤーがガッチリと固定していた。そして腰の右から左へ太いボルトが貫通し、シーツを血が黒く染めていた。血の臭いなのか、薬の臭いなのか、じっとりとした嫌な匂いが部屋に充満していた。映画の野戦病院のような光景に吐き気と汗が止まらなかった。僕の呼吸が短くそして浅くなる。事故の前の日も僕と瞬は一緒にスケボーをしていたのに。あの日、機械のように精密でそしてアグレッシブに動いていた太い足は、木の根のような色をしていた。十日前、大工の仕事で座って作業をしていた瞬の上にクレーンで吊り上げた通し柱が滑り落ちた。事故の瞬間、瞬の腰袋に入っていたトンカチの鋼が真っ二つになったそうだ。今瞬の腰はどうなっているのか僕には想像ができなかった。鋼でできたトンカチが耐えられない衝撃が僕の友達を襲ったんだ。血で汚れたシーツを見ると僕の心臓は体に血を送るのをやめて、手足が痺れた。こんなに酷いことになっているなんて僕は知らなかった。柱の下敷きになったって聞いた時は、ちょっとした骨折ぐらいだと思っていた。それなのに現実は...この匂いと、血の色に僕は怯えていて、ショックで立っているのがやっとだった。それなのに瞬はいつもと変わらずに明るく話す。
「手術受けてずっと面会できなくて、でやっと昨日面会できるようになったんだけどさ、マリーが昨日面会に来てくれて、でビックリしたよ!マリーこのタイミングでタトゥー入れてたからね!!俺がさーずっとタトゥー入れないでって反対してたの、で、俺が入院して今しかないって急いで入れに行ったんだよ!絶対に今じゃなくない?」
「違うから!瞬が入院したから私が強く生きなきゃと思って強くなる決意として入れたの!」
「強くなるって、マリーがなんのタトゥー入れたと思う?、、、ポッチャマだからね!!!ポケモンのポッチャマ!ポッチャマ弱いだろ!!強く生きたいのなら、エンペルトでよくない?」
「エンペルト可愛くないもん!!」
マリーがそう言って大きな口で笑い、そんなマリーの顔を覗きこんで瞬が笑い、二人で顔を見合わせてまた大きく笑った。そしてもっと大きな声で瞬が僕に言った。
「俺のためにとか言ってるけど、絶対にタトゥー入れたいだけだよね!どう思うユユ?」
「ちょっと飲み物買いに行ってくるよ」
僕はそう言ってこの病室から出ようとした。僕にはこれ以上元気な瞬の姿を見る勇気が無かった。
「私、売店の場所教えるよ」
マリーがそう言って僕と二人で病室を出た。病室を出るとマリーの顔から力がなくなって、歩いてる速度が段々と遅くなって立ち止まり、壁にもだれて独り言ののように話し出した。
「あのクレーンの運転手殺してやる、そう言ったらね、かわいそうだろって言うんだよ。あいつ本当に頭おかしいよね、、、、、、瞬ね、もう歩けないんだって」
そう言うと、マリーが泣き出した。震える小さな手で顔をおおいながら。泣きじゃくるマリーの肩を支えて
「大丈夫だよ、大丈夫だよ、、、瞬には俺もマリーもついてるんだからさ、、、」
僕はマリーに何かしてあげたいけど、何をしていいのか分からずに、ただソワソワしていた。そんな僕にマリーが。
「ユユは瞬の所にいてあげて、私は涙が出なくなったら戻るから。」
僕は一人で病室に戻った。
「ユユそのでかい袋何入ってんの?」
「プレゼント」
そう言ってずっと背中に背負っていた袋を僕は瞬に渡した。瞬が袋を開いて笑顔になって顔を上げて言う。
「ガールのスケボーじゃん。マジでくれるの?...でもこれ、、、マリーにあげていい?あいつも始めたがってたから...今度さ、マリーをスケボーに連れて行ってあげて」
瞬が無垢な笑顔でそう言った。なんて残酷なプレゼントを渡してしまったんだ。今度っていつだ?自分がバカすぎて情けなかった。瞬が、優しくて、明るくて、涙を我慢できなかった。どんなに強く我慢しても、涙を止められなかった。こんなに優しい瞬がどうして。悔しくて悔しくて、何が悔しいのかも解らなかった。そんな僕の顔を見て瞬が言った。
「ごめんね、ユユ」
「いや...」
何でお前が謝るんだよ、そう言ったいのに声が出なかった。瞬はゆっくりと穏やかに話し出した
「全部なくなったな、、、全部だ、仕事も、ユユも、マリーも全部だ」
「俺とマリーはまだいるだろ」
自分でもびっくりするほど大きな声が出た。でも瞬は驚きもしないで続けた
「いいんだよ、俺は悪い奴なんだよ、いろんな人を殴ってきた。ユユお前は俺のことを友達だって言ってくれるけど、実際は違ったよ、対等なんかじゃなかった、ユユは与える人間で、俺は奪う人間だ。お前とマリーは俺の憧れなんだよ、、、」
「関係ねーよ友達だろ、欲しいもんなら全部やるよ、奪ってけよ、、、」
僕の言葉を聞いた瞬が大きな声で叫んだ、くしゃくしゃの顔で、大粒の涙を流しながら。
「お前達から何も奪いたくないんだよ俺んなかと一緒にいたら、、、」
痛くて長い沈黙が続いた。すると、看護師が入ってきて、
「外で待っていてください」
そう言って、僕は病室を出された。病室の中の会話が廊下まで聞こえた。
「ア゛ア゛ァーー」
「少しだけ我慢してください」
「ア゛ア゛ァーー」
まるで洞窟の中で大きな獣が叫ぶような声が音のない廊下に響いて、鳥肌だらけの私の全身をチクチク刺した。下を見るとスニーカーに汚れがついていた。瞬ははもう履くことも出来ないスニーカーに。
この日僕は強く誓った。どんな瞬間も与える側の人間であろうと。奪われようが、騙されようが関係ない、底なしの情熱と笑顔で人に寄り添うんだよ、優しさをわけた人が遠慮しないように、卑屈にならないように、、、
過去や立場や状況は全て関係ない、この地球に不幸になっていい人間なんて一人もいない。笑顔が似合わない人間なんて一人もいない。だから、だから、僕と出会った人は全員まとめて笑顔にしたい。
そしてあの日から7年がたった今。他人への理解も、人を笑顔にするスキルも、エッチなスキルも深まった。是非ともご予約ください。何かに疲れたあなたの心も体も僕が温めて、笑顔にいたします。損はさせません。面白くて、優しくて、甘くて、ドキッとして、エッチで、心地いい痺れが襲うそんな時間を二人で過ごしませんか?
最新写メ日記
月別アーカイブ
全在籍セラピスト最新写メ日記
秘密基地グループ
-
東京エリア
東京秘密基地本店 渋谷秘密基地 新宿秘密基地 池袋秘密基地 立川秘密基地 上野秘密基地 品川秘密基地 錦糸町秘密基地 八王子秘密基地 町田秘密基地 六本木秘密基地 銀座秘密基地 青山秘密基地 世田谷秘密基地 赤坂秘密基地 吉祥寺秘密基地 恵比寿秘密基地 赤羽秘密基地 西麻布秘密基地 新大久保秘密基地 中野秘密基地 -
関東エリア
横浜秘密基地 千葉秘密基地 さいたま秘密基地 宇都宮秘密基地 川崎秘密基地 群馬秘密基地 西川口秘密基地 湘南秘密基地 茨城秘密基地 船橋秘密基地 大宮秘密基地 柏秘密基地 松戸秘密基地 水戸秘密基地 舞浜秘密基地 越谷秘密基地準備中 -
北海道・東北エリア
札幌秘密基地 仙台秘密基地 郡山秘密基地 山形秘密基地 岩手秘密基地 青森秘密基地募集中 秋田秘密基地募集中 -
北陸・甲信越エリア
新潟秘密基地 長野秘密基地 甲府秘密基地 金沢秘密基地募集中 富山秘密基地募集中 福井秘密基地募集中 -
東海エリア
静岡秘密基地 名古屋秘密基地 三重秘密基地 岐阜秘密基地 浜松秘密基地 岡崎秘密基地 豊橋秘密基地 藤が丘秘密基地 -
関西エリア
大阪秘密基地 神戸秘密基地 なんば秘密基地 京都秘密基地 梅田秘密基地 堺東秘密基地 京橋秘密基地 滋賀秘密基地募集中 奈良秘密基地募集中 和歌山秘密基地募集中 -
中国エリア
広島秘密基地 岡山秘密基地 山口秘密基地 出雲秘密基地募集中 鳥取秘密基地募集中 -
四国エリア
香川秘密基地 徳島秘密基地 高知秘密基地募集中 松山秘密基地募集中 -
九州・沖縄エリア
博多秘密基地 沖縄秘密基地 鹿児島秘密基地 大分秘密基地 北九州秘密基地 宮崎秘密基地 佐賀秘密基地 熊本秘密基地 長崎秘密基地 中洲秘密基地 久留米秘密基地募集中