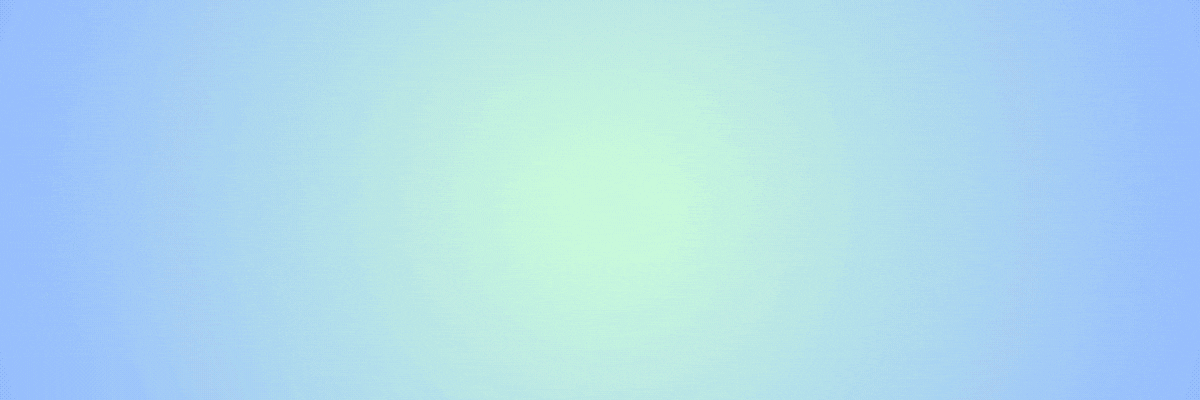12/11 07:04 UP!
『セラピストという存在』

昨日は秘密基地グループの忘年会へ。
休日は家で読書か映画鑑賞と相場は決まっている僕にとって、こういった晴れの場に出るのは緊張やら不安やらで中々に忙しない。
虚栄の限りを尽くした乱痴気騒ぎという印象と、東京はこれほどまでに素敵な人たちで溢れていたのかという感動との間で揺れ動いていた頃、あるセラピストS氏と落ち合う。
「退屈してる?」
「まあね」
「フロアをぐるっと回ろう。10分後に戻ってくるまでに何人のお客様と話せたか、勝負だ」
「会話で重要なのは質だよ。量じゃない」
「でも、なにもしなけりゃどっちも得られない」
「確かにね」
そんな訳で、奇妙なゲームが開始されたのである。
僕のポリシーとして、人に話しかけるときは、
・相手の特徴を観察する
・相手の斜め前から声をかける
・相手の視点に立って話を始める
という3つのルールを決めている。決めているのだ、が、なぜだろう。
いざ話しかける段になると、身体が強張って動けなくなってしまう。
別にビビってなどいませんよとばかりにフロアの天井に吊るされた龍の飾り付けをこれ見よがしに眺めてみても、現状は一向に変わらない。
動かなければ。
「あの」
いつになく真剣な表情で天井を眺めていた僕に、ひとりのお客様が話しかけてくれた。
「ながるさんですね。いつも投稿拝見してます」
「えぁ、ありがとうございます」
我ながら最低な初動である。次はどうする、とりあえず天気の話題か? いや、感謝を示す意味でもどこに興味を持ってくれたかを聞くべきだろう、などと考えているうちになんとなく会話のキャッチボールが成立していた。
近くのソファに腰掛けて、色々なことを話す。好きな小説の話、美術館の話、椎名林檎の話、クリスマスの過ごし方について、どのように生きてどこで死にたいか……人と意見を交わすのはいつでも新鮮な思いがする。
結局のところ、何事も上手くやろうと意気込んでいては、上手くいくものもいかなくなるのだ。基地での日々はつねにドラマチックで、学びに富んでいる。
不意にぽんと僕の肩に手が置かれる。気がつくと30分以上が経過していて、呆れた表情でセラピストS氏がこちらをじっと見ていた。
「6人が限度だったよ。それにしても、君は少々馬鹿にしてるんじゃないか?」
「なんだって?」
「だって、君はずっとひとりだったじゃないか」
慌てて正面に向き直ると、そこにはぽっかりと空席を呈したソファーがあるだけだった。
背中のあたりがぞわりとする。
「……なあ、いま何人と話したと言った?」
「そりゃ、ええと……あれ、何人だっけ?」
そうか、なるほど。謎は解けた。
セラピストという存在は、常に利用されるお客様ひとりだけのもの。
"他のお客様"という概念など、存在してはならないのだ。
※この物語はフィクションです。
休日は家で読書か映画鑑賞と相場は決まっている僕にとって、こういった晴れの場に出るのは緊張やら不安やらで中々に忙しない。
虚栄の限りを尽くした乱痴気騒ぎという印象と、東京はこれほどまでに素敵な人たちで溢れていたのかという感動との間で揺れ動いていた頃、あるセラピストS氏と落ち合う。
「退屈してる?」
「まあね」
「フロアをぐるっと回ろう。10分後に戻ってくるまでに何人のお客様と話せたか、勝負だ」
「会話で重要なのは質だよ。量じゃない」
「でも、なにもしなけりゃどっちも得られない」
「確かにね」
そんな訳で、奇妙なゲームが開始されたのである。
僕のポリシーとして、人に話しかけるときは、
・相手の特徴を観察する
・相手の斜め前から声をかける
・相手の視点に立って話を始める
という3つのルールを決めている。決めているのだ、が、なぜだろう。
いざ話しかける段になると、身体が強張って動けなくなってしまう。
別にビビってなどいませんよとばかりにフロアの天井に吊るされた龍の飾り付けをこれ見よがしに眺めてみても、現状は一向に変わらない。
動かなければ。
「あの」
いつになく真剣な表情で天井を眺めていた僕に、ひとりのお客様が話しかけてくれた。
「ながるさんですね。いつも投稿拝見してます」
「えぁ、ありがとうございます」
我ながら最低な初動である。次はどうする、とりあえず天気の話題か? いや、感謝を示す意味でもどこに興味を持ってくれたかを聞くべきだろう、などと考えているうちになんとなく会話のキャッチボールが成立していた。
近くのソファに腰掛けて、色々なことを話す。好きな小説の話、美術館の話、椎名林檎の話、クリスマスの過ごし方について、どのように生きてどこで死にたいか……人と意見を交わすのはいつでも新鮮な思いがする。
結局のところ、何事も上手くやろうと意気込んでいては、上手くいくものもいかなくなるのだ。基地での日々はつねにドラマチックで、学びに富んでいる。
不意にぽんと僕の肩に手が置かれる。気がつくと30分以上が経過していて、呆れた表情でセラピストS氏がこちらをじっと見ていた。
「6人が限度だったよ。それにしても、君は少々馬鹿にしてるんじゃないか?」
「なんだって?」
「だって、君はずっとひとりだったじゃないか」
慌てて正面に向き直ると、そこにはぽっかりと空席を呈したソファーがあるだけだった。
背中のあたりがぞわりとする。
「……なあ、いま何人と話したと言った?」
「そりゃ、ええと……あれ、何人だっけ?」
そうか、なるほど。謎は解けた。
セラピストという存在は、常に利用されるお客様ひとりだけのもの。
"他のお客様"という概念など、存在してはならないのだ。
※この物語はフィクションです。